-
業種・地域から探す
続きの記事
京都産業界
変革をも勝機と捉え、新たな価値生み出す-京都企業トップに聞く(2)
三洋化成社長 樋口 章憲 氏/中国経済対応が将来左右
-

三洋化成社長 樋口 章憲 氏
-事業を取り巻く環境は。
「中国経済の停滞で化学品を安価に大量生産する中国企業の製品が自国消費できず、国外に流出して価格競争が激化している。当社は高吸水性樹脂(SAP)の事業撤退を決めたが、そのような事業環境を踏まえてのこと。コモディティー製品は中国企業に勝てない前提で経営戦略を立てる。中国経済の難しさにどう対応するかが、自社のみならず化学産業の将来を左右すると考える。自動車の燃費向上に寄与する潤滑油添加剤などに代表されるような、中国の今の技術レベルでは難しい製品の販売に注力する」
-人工たんぱく質「シルクエラスチン」は事業化への取り組みが順調に進んでいます。
「このほど科研製薬と創傷治療用シート材料に関し、国内での独占的販売権に関するライセンス契約を結んだ。この取り組みをしっかりと成功させることが、体内にある半月板の損傷治療用など、シルクエラスチンの適用部位を広げるための第一歩となる」
-工場の働き方改革をどう進めますか。
「女性や高齢者も働きやすい環境整備が必要だ。生産品目や設備による部分もあるが、ENEOSマテリアル(東京都港区)との共同出資会社『サン・ペトロケミカル』(茨城県神栖市)は女性比率が高く、モニタリングシステムを整備して自動化を進め、定期修理では飛行ロボット(ドローン)を活用している。同社を見本にしながら、環境を整備していく」
宝ホールディングス社長 木村 睦 氏/〝外食で和酒〟の市場強化
-

宝ホールディングス社長 木村 睦 氏
-焼酎や清酒など「和酒」の国内における成長戦略は。
「少子化に加え、1人当たりのアルコール消費量が減少している。大量生産で安く売る製品では直近5-10年は通用しても、その先はやっていけない。ボリュームに頼らず、付加価値の高い製品を適正量販売することで、利益を確保していく」
-和酒と和食とで相乗効果を発揮し、海外で日本食材卸事業を拡大しています。
「当社のシェアは欧州がトップで、北米は3位、世界でも3位につけている。だが、世界シェアトップの企業とは同事業の売上高が3-4倍ほど離れており、トップ企業の得意分野に当社が力を入れるのは合理的ではない。当社は引き続きレストラン向けを中心に事業を伸ばし、外食で和酒を楽しんでもらいたいと考えている。エリアでは、北米の強化が最優先。北米の日本食市場が拡大する中、当社拠点がない空白地帯もあり、十分やりきったとは言えない」
-ワクチン生産体制強化を目的にした政府の補助金を活用し、タカラバイオが新棟を2027年に稼働します。
「有事はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンなどの製造拠点として機能させる一方、平時は企業活動に利用できる。世界でバイオテクノロジーの研究開発が盛んなことから、新棟が稼働すれば当社の競争力は相当なものとなる。試薬や機器、開発製造受託(CDMO)事業で、バイオテクノロジーの研究開発をしっかりと側面支援していく」
京セラ社長 谷本 秀夫 氏/研究テーマは選択と集中
-

京セラ社長 谷本 秀夫 氏
-パッケージなど、半導体分野の現状や中長期の見込みは。
「2023年度下期から落ち込んだ需要の回復は24年度下期を見込んでいたが、25年度以降にずれ込む。ハイエンドの半導体製造装置向けに供給するセラミック部品は少しだが回復しており、半導体の設備投資の再開がうかがえる。有機パッケージは人工知能(AI)半導体のトップメーカー向けの受注がとれていないのが課題だが、後発への販売活動を進めている。生産拡大や売り上げへの貢献は1年以上後になるため、今は我慢の時だ」
-4月にコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)ファンドを組成しました。
「医療など、自社で幅広い研究開発テーマに取り組んできたが、浅く広くなり成果につながりづらかった。そのため、2年ほど前から研究テーマの選択と集中を進めてきた。当社のコア事業から外れる研究テーマはCVCを通じて投資し、芽が育ったときに提携や当社グループ化につなげる方が現実的。当社は半導体分野やセラミック、スマートファクトリー実現に向けた研究や開発に集中する」
-宇宙分野の開拓に向けた取り組みは。
「宇宙で使われる部品は温度に対する形状変化が小さいことが求められ、当社のセラミック材料が使われる機会が増えてきた。人工衛星の増加で高性能な水晶発振部品も工業生産しないと間に合わないなど市場環境が変わってきており、宇宙分野が拡大基調にあると実感している」
TOWA社長 岡田 博和 氏/HBM多層化実現に貢献
-
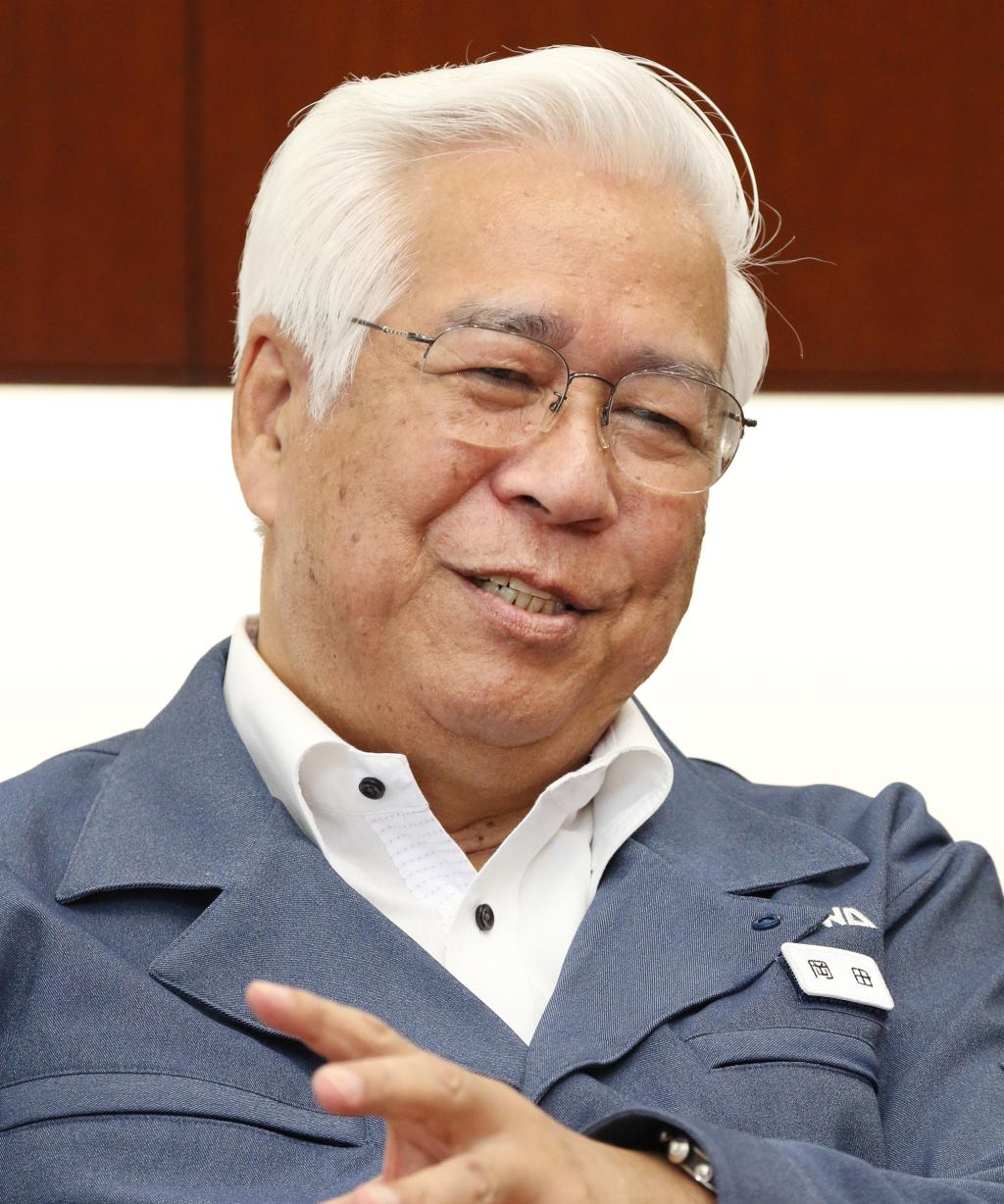
TOWA社長 岡田 博和 氏
-世界シェアトップの半導体モールディング装置の事業環境は。
「スマートフォンのメモリー半導体向け装置の引き合いは全く動きがない。2024年夏頃に設備投資が再開すると考えていたが、いつになるか不透明だ。一方、好調なのが生成人工知能(AI)用の広帯域メモリー(HBM)向け。中国は経済全体が減速するが、米中対立を背景とした半導体国産化の動きが進み、他の半導体製造装置メーカー同様、当社装置需要も堅調だ」
-HBM向け装置の現状や展望は。
「23年度の装置販売台数は20台ほどだった。本年度は若干下回るが、HBMの需要急拡大のピークは26、27年頃の見込みで、その後も成長が続く。今後はスマートフォンやパソコン向けメモリー半導体もHBMに置き換わっていく。そのため、当社は25年3月に韓国で新工場を稼働予定だ。主流の8層から成るHBMや12層の次世代品の実現には当社の技術が大きく貢献した。相当ハードルが高いが、さらなる多層化にも寄与したい」
-インドでは政府が半導体産業の育成を図っています。
「昨年は半導体産業の立ち上がりはまだまだ先だと思っていたが、現在は想定以上の早さを感じる。政府の後押しや半導体関連設備の進化、人材の豊富さなどを踏まえると、インド市場は間違いなく伸びる。ただ国土が広く、政策も(エリアごとに)異なるため、顧客拠点ごとに営業やサービス対応のやり方を変える必要がある」
日新電機社長 松下 芳弘 氏/グループ企業と連携加速
-

日新電機社長 松下 芳弘 氏
-受変電設備やそれらを制御するシステムなど、電力品質安定化につながる電力・環境システムを手がけます。足元の事業環境は。
「国内は工場などの民需が特に堅調。半導体やデータセンター市場が活況で電力需要が高まり、電力関連への投資が増えている。電力会社向けも好調だ。2023年から始まった電力会社が国に対して5年間の投資計画を事前に伝え、承認を得てから実行に移すレベニューキャップ制度により、投資が景気に左右されにくくなり、安定した受注を生んでいる。地震など頻発する自然災害への対応や、再生可能エネルギーの普及拡大に関連した需要も増えてきている」
-次代の成長を見据え、親会社の住友電気工業との連携を加速させます。
「当社と住友電工の連携を強化するため『日新住電エネルギーシステム開発センター』を開設した。期待するシナジーは短、中、長期で複数ある。短期的なものだと、住友電工が強みとする材料技術を生かし、材料面で競合他社と差別化できる電力機器の開発が挙げられる。また、当社が主力とする電力・環境システム事業以外の分野、例えば、半導体製造に使うイオン注入装置などのビーム・プラズマ事業でのシナジー発揮も視野に入れる」
-グローバル戦略でも両者のシナジー発揮が期待できます。
「グローバルに事業拡大する上で、住友電工が世界中に展開する拠点を、マーケティングや顧客対応で活用するのも一つの手だ」
京都銀行頭取 安井 幹也 氏/事業再生、伴走支援に本腰
-

京都銀行頭取 安井 幹也 氏
-観光関連産業が回復した一方、モノづくり企業は好不調が混在しています。
「人手不足やコスト高、為替変動、人をつなぎ留めるための賃上げなど経営課題はさまざま。価格転嫁できた中小企業は良いが、認めてもらえていない場合は厳しい印象だ。人手不足、事業承継、跡継ぎ問題を抱える企業は多い。課題を抱える企業に寄り添い、次につながる提案、事業再生、伴走支援する事業に本腰を入れている」
-地域社会や顧客課題を解決する非金融機能を拡充しています。
「当行は地域と共に歩んでいる銀行。顧客の悩みや課題が多様化する中、グループ会社の専門スタッフと一緒に出向いて提案を行っていく。政策投資株の縮減で生まれた資金を、次を担うスタートアップに投資、支援する動きも加速する」
-一方、〝金利のある世界〟に戻りました。
「追い風で、預金の重要性が高まる。広域店舗網を維持してきたことが強みになる。ただ、大半の行員は預金を追いかけた経験が無い。銀行の本業と言われる業務への感度も高め、預けて頂くことへの感謝をしっかりと持ってもらう。メーン口座指定につながる住宅ローンも非常に大事だ」
-製造業の国内回帰の動きを聞きます。
「国内投資もあるが、中国から東南アジアに移す所も多いと感じる。インドの話もよく聞く。当行も先日、若手に現地状況視察へ行ってもらった。近く、国際営業担当役員にも深く見て、詳しく聞きに行ってもらう予定だ」

