-
業種・地域から探す
続きの記事
神奈川県特集
未来を担う人を育むー神奈川の大学ー
【関東学院大学】社会連携教育で地域と関わり合う
関東学院大学は企業や自治体、地域と深く関わり合う社会連携教育に力を注いでいる。社会とつながることで「自ら課題を発見する力」、「情報を整理して解決方法を導く力」、「多様な人々と協働できる力」を育む。時代とともに社会が抱く課題と向き合い、実践的な能力と技術を磨く。特に工学分野では前身の専門学校時代から産学連携の先駆けとなり、1962年には世界で初めてプラスチックのめっき加工を実用化している。教育・研究の両面で地域に貢献する大学として存在感を示す。
産学連携の草分け 研究成果で地域貢献
-
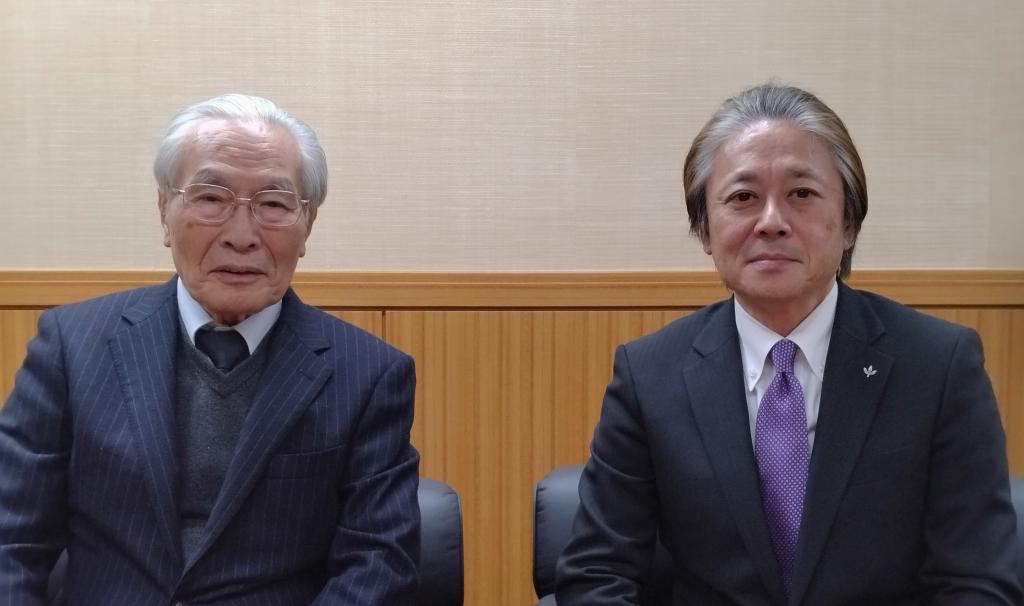
小山嚴也学長㊨と本間英夫特別栄誉教授
関東学院大学には、産学連携の伝統が脈々と息づいている。一般に大学の産学連携は、企業共同研究を始める際に機密保持契約を結ぶことが多い。この方法だと研究成果が1社にとどまってしまい、産業界への波及効果は限られる。それに対し、同大の材料・表面工学研究所では、多くの企業が参加できるコンソーシアムを作り、大学のシーズを参加企業に幅広く活用してもらう機会を設けている。
全学を挙げて社会連携教育に取り組む小山嚴也学長は「すべての課題は教室や研究室の中ではなく、社会にあると考えている。だからこそ、大学という機関を積極的に利用し、相談してほしい」と話す。そして、材料・表面工学研究所で培った実績から「めっきはあらゆる領域で必要とされる要素技術。スマートフォンはもちろん、身近な存在となった最先端生成AI(人工知能)も、めっき技術がなければ社会実装はできない。学生の理系離れが目立つ中で10年、20年後に表面工学の研究者になり、活躍する学生が増えていることを願う」と期待する。
その期待を後押しするように、これまでに同大はめっき加工を中心に200件近い特許を出願。1946年に学内に設立された実習工場が原点だ。のちに関東化成工業(神奈川県横須賀市)としても事業化され、大学発ベンチャーの先鞭をつけた。
プラスチックめっきを実用化し、バンパーなど自動車部品の軽量化に大きく貢献。その後、プリント基板や、基板のスルーホールめっき、半導体の金属配線などエレクトロニクス分野の表面処理技術を発展させてきた。
建学の精神「人になれ、奉仕せよ」体現
-

夏休み期間中、子ども向け実験教室を開催(材料・表面工学研究所)
表面処理研究の第一人者で、長年にわたって同大の材料・表面工学研究所を率いてきた本間英夫特別栄誉教授は「本研究所は“産学協同の草分け”との自負がある。産業界との連携をさらに緊密にし、学生の教育研究に生かしていきたい」と話す。さらに、「コンソーシアムの参加企業は特許使用料を払わずに利用でき、特許の年間維持費や奨学金という形で学生を支援していただいている。こうした取組みによって1社単独の産学連携にとどまることなく、産業界に広く研究成果が波及する」と説明する。まさに同大の建学の精神「人になれ、奉仕せよ」を体現するものだろう。
その実績を裏付けるように文部科学省から毎年公表される調査「大学等における産学連携等実施状況について」にランクインする常連だ。2月に発表された2023年度実績では特許権実施等件数が全国7位(私大1位)、知的財産権等収入が同14位(同4位)だった。
今後も地域や産業界に貢献する大学として、歩んでいく。
【神奈川大学】SDGs、多視点からアプローチ
神奈川大学は、SDGs(国連の持続可能な開発目標)に貢献する取り組みを教育・研究・施設の面から推進している。SDGsの目標は、主体的に新たな価値を創造する人材の育成を通じて未来社会の発展と安定に寄与することを使命に掲げる同大学の建学の精神に合致。SDGsに関する学生の優れたアイデアや取り組みを表彰する「神奈川大学SDGsアワード」やカーボンニュートラル推進の取り組みを通じて、地球規模の課題への解決策をさまざまな側面から探求する教育・研究活動を実践する。
学生の自由なアイデア引き出す
-

24年度神奈川大学SDGsアワードの最優秀賞チームメンバーと小熊誠学長(左から2人目)
神奈川大学のSDGsに関する取り組みは外部からも高く評価されている。英国の高等教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)が世界の大学の社会貢献度をSDGsの枠組みで評価する「THE Impact Rankings2024」で同大学は、目標6(安全な水とトイレを世界中に)で世界201ー300位、目標2(飢餓をゼロに)など五つの目標で世界301ー400位という高い評価を受けた。総合でも世界801ー1000位にランキングされ、普段の研究活動や、自治体・地元コミュニティーとの連携活動などが評価された。
学生を対象に、SDGsの認知と意識を高める取り組みも推進する。SDGsに関する学生の優れたアイデアや取り組みを表彰する「神奈川大学SDGsアワード」を21年度にスタート。以降毎年開催しており、24年度で4回目を迎えた。
学生のチームを対象に、SDGsに関連した研究活動や取り組み、課題解決に役立つアイデアを募集。書類などによる一次選考を経たチームは、毎年3月に「みなとみらいキャンパス」(横浜市西区)で行われる最終プレゼンテーションに臨む。一般観覧者も見守る中、質疑応答、審査委員による最終選考を経て受賞作品が決まる。
学生の自由な発想でSDGs推進のアイデアが創出されており、例えば24年度最優秀賞チームは、ろう者と共に学ぶことを目的に、手話を読み取ったり音声と相互変換したりする技術を組み込んだARグラスを提案。日頃の研究室の活動において、ろう者も円滑に議論に参加できる方法を考えた。
熱エネルギーの脱炭素化に貢献
-

神奈川大学みなとみらいキャンパス
また神奈川大学は、基本方針「神奈川大学カーボンニュートラル・トライアングル」により、「教育」「研究」「施設」の視点から二酸化炭素(CO2)排出量の削減を推進し、創立100周年となる28年度までにCO2排出量を「13年度比50%削減」、50年までに「カーボンニュートラル実現」を目指している。
その一環で、みなとみらい(MM)21地区に開設したみなとみらいキャンパスでは、脱炭素化に寄与する地域の取り組みに参画する。同地区でオフィスビルの冷暖房に利用する熱エネルギーの脱炭素化に向け、カーボン・オフセットを活用する取り組みが24年に始まり、みなとみらいキャンパスもこれに参加する。
MM21地区のCO2排出量の約3割は、冷水や蒸気などをつくる熱エネルギーに起因すると試算される。MM21地区で熱供給事業を手がける事業者「みなとみらい21熱供給」では、熱のカーボン・オフセットサービスを24年に開始。CO2排出量を計算し、それに見合う環境価値「J―クレジット」を調達する仕組みで、神奈川大みなとみらいキャンパスを含めMM21地区内の複数の施設が同サービスを活用する。これにより同地区の熱エネルギーのCO2排出量を約2割削減可能であり、熱エネルギーに関して日本最大規模の脱炭素の取り組みとなる。



