-
業種・地域から探す
続きの記事
茨城県産業
将来の飛躍に向けて挑戦を続ける茨城県産業界。原材料やエネルギー価格の高騰を受けて景気の先行きには不透明感が漂うものの、中長期的の経営基盤強化を見据えた人材育成や、新規事業創出を目指す取り組みが官民で着実に進展している。今回の「茨城県産業特集」では、大井川和彦茨城県知事のメッセージのほか、県内の企業立地動向、県内の国立大学の動向や大手企業の地域貢献などを10ページにわたり紹介する。
茨城県 主要8大学学長が語る 地域との共創
冒険する大学へ-Next50への挑戦- 筑波大学 永田 恭介 学長
-

AIパートナーシップ調印式の様子
昨年、開学50周年を迎えた本学は、次の50年(Next 50)を見据え、社会の要請の一歩先へ踏み出し、未来を創造する「冒険する大学」として進化する。
社会課題解決の基盤は研究推進である。今年4月、米国ワシントン大学、NVIDIA、AmazonとAI分野でのパートナーシップを締結した。共同研究や人材育成などを通じ、本学にAI拠点を形成し、地球規模課題の解決に貢献する。企業のR&D部門を本学に招聘し、基礎研究からビジネス創出までを一貫して行う施設(IMAGINE THE FUTURE.Forum)の建設も予定しており、研究成果の社会実装を通じた社会との共創に取り組む。
質の高い教育は未来への礎となる。本学では、PBL型の少人数科目(学問探究チュートリアル)を今年度から学士課程に開講した。今後は学生宿舎を教育効果をも意図した形態にリニューアルし、学びの機会にも活用する。
今年8月、三井住友フィナンシャルグループとの間で包括連携協定を締結した。本学の知識と金融ノウハウの融合による大学経営の変革に取り組み、金融機関との新たな連携モデルを構築する。
現代の社会は固定化された概念に縛られている。本学は今後も、固定化された学問、組織、様々なシステム改革を要点と捉え、大学改革に挑戦する。
グローカル教育を通じて更なる地域貢献を目指す/常磐大学 富田 敬子 学長
-

常磐大学三和キャンパス
1983年の創立以来、常磐大学は、「実学を重んじ真摯な態度を身につけた人間を育てる」という建学の精神のもと、時代の要請に応じた課題解決型の教育を提供してきた。入学生の約9割が茨城県内の高等学校等から入学し、卒業生の約8割が茨城県内の企業等に就職しており、地域の人材を積極的に受け入れて送り出す“循環型の教育”を通じて、地域社会に貢献している。今後は、地方(ローカル)に生活の基盤を持ちつつも、世界(グローバル)を俯瞰的にとらえることができる教養人を育成(グローカル教育)し、送り出すことによって地域社会の発展向上により一層貢献したいと願っている。
この理念を具現化するため、本学では、2026年度より「グローカル人材プログラム」(仮称)を開始すべく、準備を進めている。複数の企業・自治体の協力を得て、有為な人材を育成し、地域社会に貢献しようとするものである。同プログラムでは、地域社会や文化の理解、課題の把握や解決に資する学修はもとより、留学や海外研修なども積極的に推進してゆきたい。
未来を見据え、地域とともに発展・成長する高等教育機関として、急速に変容する社会の要求に応え得る教育研究に取り組んでゆく。
「日本国際学園大学」開学/日本国際学園大学 橋本 綱夫 学長
-
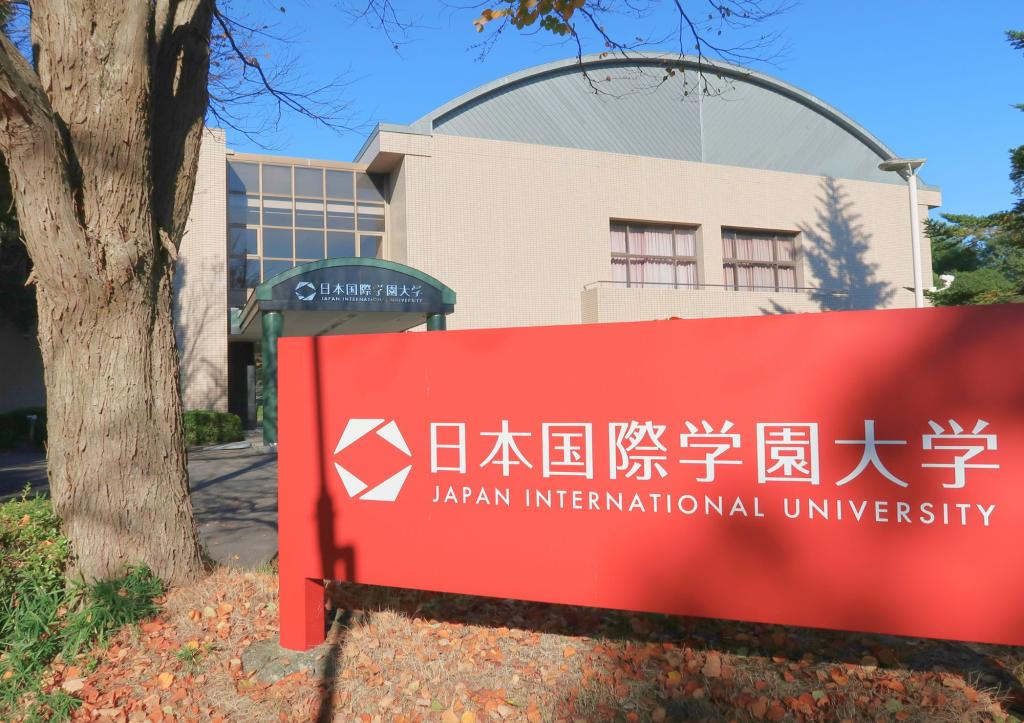
日本国際学園大学のつくばキャンパス
2024年4月に名称を新たに、「日本国際学園大学」としてスタートした。「つくばと仙台」の2キャンパス体制で新しい学びを創造 していく。
本学は、入学後すぐの海外研修を始め、海外体験、海外留学の機会を得られるよう海外研修プログラムの充実を図っている。国際化を一層進めるため、連携協定の締結を進めている。
さらに、社会が変化する中、多様な教育ニーズに対応すべくカリキュラムを大幅に刷新した。経営学、情報学、デザイン学、英語を中心として、学術教育と実学教育を一体的に提供する。デジタル化・グローバル化が進む社会で、高い技能を身につけ、国際的視野を涵養する「世界のトビラとなるような大学」になることを目指す。
また、学生の多様性も重視している。海外からの留学生は勿論、日本国内からも海外にルーツのある学生や、 普通科だけではなく専門学科や通信制・定時制からの学生にも幅広く学びの門戸を開いている。入学後もキャンパスアドバイザーが、学生一人ひとりに寄り添いサポートするなど支援制度の充実に取り組んでいる。
本学は、質の高い教育の提供や支援をし、ビジネスの世界で個性的に活躍でき、そして世界が抱えるさまざまな問題を乗り越えていく人材を育成していく 。
サプライチェーンの未来を切り拓く/流通経済大学 片山 尚登 学長
-

物流特別シンポジウム
流通経済大学は、「実業に強い人材の育成」という建学理念のもと、「実学主義」「教養教育」「少人数教育」を柱に、学生が自ら目標を掲げ、達成する力を育む教育環境を提供している。そして、2025年に開学60周年を迎えるにあたり、実学主義への取り組みをさらに深化させる。
中でも注目は、本学の付置機関「物流科学研究所」の進展である。同研究所は、日本のサプライチェーン・ロジスティクス研究の中心拠点として、研究会、シンポジウムや研究誌を通じ、「物流の2024年問題」などの課題解決に取り組んでいる。また、本学流通情報学部と連携して、茨城県の企業・団体に所属する客員講師による「地域ビジネス実践講座」などのプログラムを展開し、学生が地域や地域企業と連携しながら実学を学ぶ機会を提供している。さらに、同研究所と同学部の連携により、AI・データサイエンスとコラボした「メタバーススペース」や「トレーニングファクトリー」などの先端技術を活用した学習空間を構築し、日本のサプライチェーン・ロジスティクス、AI・データサイエンスの未来を切り拓く拠点としての役割を強化していく。
これらの取り組みを通じて、本学は地域社会に貢献すべく、次世代のイノベーションを担う実業に強い人材を育成する。
地域の価値を創出する新たなチャレンジ/茨城大学 太田 寛行 学長
-

学生と語らう太田学長(左から2番目)
創立75周年を迎え、未来へ向けた新たなチャレンジを進めた。
まず、学生たちの「こうなりたい」という願いに寄り添った教育・学生生活の統合的支援を行う拠点として、「スチューデントサクセスセンター」を新設した。加えて、新たな学部相当の組織である定員40名の地域未来共創学環を開設。この学環では、文理横断でビジネス、データサイエンスなどを学んだ学生たちが、3年次に茨城県内の企業や自治体において、有給の「コーオプ実習」に取り組む。第一期生は入学時から地域課題への関心や自らのビジョンを語っていた。今後も学修者本位の教育を強化していく。
研究面では原子科学研究教育センターを4月に開設した。さらに来年4月には、応用生物学分野から気候変動の緩和策に取り組む「グリーンバイオテクノロジー研究センター」の設置を予定している。これらに地球・地域環境共創機構、カーボンリサイクルエネルギー研究センターを加えた4つのセンターを柱に、環境とエネルギーの視点から、総合気候変動科学の創出の取り組みを力強く進めていく。その体制がようやく整った。
ステークホルダーの皆様との連携により、これらの改革を、地域の価値の創出に確実につなげていきたい。
4つの目標に基づく地域活性化とグローバル化の推進/茨城キリスト教大学 東海林 宏司 学長
-

正面から見た茨城キリスト教キャンパス
本年4月の学長就任にあたって、4つの目標を掲げた。
-「コミュニティーの再構築」。コロナ禍により生じた人間関係の希薄化の解消を図る。まずは本学内のチームワークを強化し直し、学園内中高やこども園との関係も再点検し、総合学園としてのメリットを最大化していく。
-「『本学らしさ』を再点検し、研究・教育・社会貢献の原点に立ち返ること」。現在進行系の具体例として、「IC with U プロジェクト」と題した、外国にルーツのある子どもたちに対する日本語学習支援等を通じた《多文化協働クリエーター》育成の取り組みが挙げられる。
-「DXの推進」コロナ禍により、教育分野におけるDXは進展した。コロナ後はBYOD(Bring Your Own Device)方針を継続し、情報機器の教育への活用を更に進めていく。
-「グローバル化の次なる段階へ」。本学の特色である国際交流を強化していくには、今後の世界情勢を見据える視点が欠かせない。英語が公用語の一つであり、今後大きな経済発展も見込まれるインドには、日本語教育を実践している大学もあり、交流先の有力開拓国と位置づけている。
4つの目標を通じて、本学が立地する日立市を中心とした県北・県央地域の活性化およびグローバル化を推進していきたい。
ダイバーシティ&インクルージョンを推進する大学/筑波技術大学 石原 保志 学長
-

新学部(共生社会創成学部)の模擬授業の様子
我が国で唯一の障害者のための大学である。学部学生の入学資格として、聴覚または視覚に障害があることを要件としている。2025年度から新学部「共生社会創成学部」がスタートする。同学部は、障害のある学生が社会で生きていく力を身に着けるとともに、職業分野を中心に、卒業生が社会で活躍することによって、真にインクルーシブな社会を構築、発展させることを目標としている。文理融合、社会モデルとしての障害、セルフアドボカシーがキーワードとなる、Well-Beingの原点ともいえる学問分野である。この他、既存学部には、デザイン、建築、機械、情報、鍼灸、理学療法といった実学系の学科がある。大学院情報アクセシビリティ専攻は、本学で唯一、健常者の入学が可能で、障害者を支援する高度専門人材の育成と最新の障害者支援技術について研究を行っている。また学生と教職員が一丸となり、「生活」(つくば市等:バリアフリー環境の整備)、「安全」(気象台等:緊急警報伝達の工夫)、「情報通信」(日本財団電話リレーサービス等:手話、音声、文字、各々の変換通訳)、「スポーツ」(デフリンピック2025東京大会への参画)等々、多様な分野で社会との共創を図っている。
心に寄り添い多職種連携が実践できる医療専門職の育成/茨城県立医療大学 阿部慎司学長
-

茨城県立医療大学のキャンパス
本学は「心の通い合う医療の実現」を理念に、地域社会において広く活躍できる質の高い医療専門職の育成を目的として、1995年4月に開学し、2025年に開学30周年を迎える。
本学の特色として、単科の公立保健医療系大学として全国でも唯一のリハビリテーションを主とする付属病院を有しており、質の高い臨床実習の実践の場・臨床研究の場を確保するとともに、ロボットリハビリテーションの臨床応用など、最新のリハビリテーション医療の推進と地域医療への貢献に努めている。
学部教育では、高度な知識と実践能力を有するバランスのとれた医療人を育てるためにOSCE(客観的臨床能力試験)をいち早く取れ入れているほか、国際的、地域社会的な視点を養う「国際多職種協働実習」、「地域多職種協働実習」など、多職種連携教育にも積極的に取り組んでいる。
大学院では、24年度から博士前期課程に新たに医科学領域を設け、3専攻から1専攻4領域に改組し、分野横断的な教育研究を展開している。
社会情勢の急速な変化に伴い様々な課題が顕在化する中、益々重要となる、患者さんなどの心に寄り添う気持ちを持って多職種連携が実践できる医療専門職の養成に努めていく。

