-
業種・地域から探す
続きの記事
茨城県産業
将来の飛躍に向けて挑戦を続ける茨城県産業界。原材料やエネルギー価格の高騰を受けて景気の先行きには不透明感が漂うものの、中長期的の経営基盤強化を見据えた人材育成や、新規事業創出を目指す取り組みが官民で着実に進展している。今回の「茨城県産業特集」では、大井川和彦茨城県知事のメッセージのほか、県内の企業立地動向、県内の国立大学の動向や大手企業の地域貢献などを10ページにわたり紹介する。
基調講演 日立グループ「創業の精神」の継承と発展
日立が大切にしてきた企業理念と創業の精神の継承/
日立オリジンパーク小平記念館館長 和久井 勇人 氏
-

日立オリジンパーク小平記念館館長 和久井 勇人 氏
今年で創業から114年目を迎える日立は、現在売り上げと従業員数ともに6割を海外が占めています。しかし創業のルーツをたどると、弊社は日立鉱山(茨城県日立市)で電気機械の修理をする小さな小屋から始まりました。日立が創業時から大切にしてきた企業理念が「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」です。時代を経て事業の在り方が変わっても、自分たちの手で日本のモノづくりや社会に貢献したいという創業者の思いは変わらずに受け継がれています。
私たちが企業理念と同じく大切にしているのが日立創業の精神です。創業以来、企業としての発展を支えてきた先人たちが大切に育んできた「和・誠・開拓者精神」。企業理念と創業の精神、これからの日立のあるべき姿を定義した日立グループ・ビジョン。これらは体系化され、「日立グループ・アイデンティティ」として600社以上ある国内外のグループ企業と共有されています。
今日は、創業者の小平浪平の代表的な言葉をご紹介します。一つ目は、「日本で作るようにしなくてはならぬ」。1905年、外国製品に頼っている発電所の現場を目の当たりにした際に話した言葉で、創業に向けた強い決意を感じます。二つ目は、「われわれは、京浜地方の復興を第一の任務とすべきである」。関東大震災で京浜地方が大きく被災したとき、小平自ら社員に対して、他の地域の注文を断ってでも被災地の復興を優先せよと語りかけました。その姿勢には日立の社会イノベーションのルーツが感じられます。
2021年に開館した日立オリジンパークは、日立の歴史と創業の精神を現代に伝える場所。まさに原点です。創業者の思いを美化することなく、そのままの姿で伝えることで、企業としてこんにちまで変えてこなかったもの、変えてきたものが見えてきます。
日立が「第二の創業」として茨城県内で進めているプロジェクト/
日立製作所 ひたち協創プロジェクト推進本部 本部長 佐野 豊 氏
-
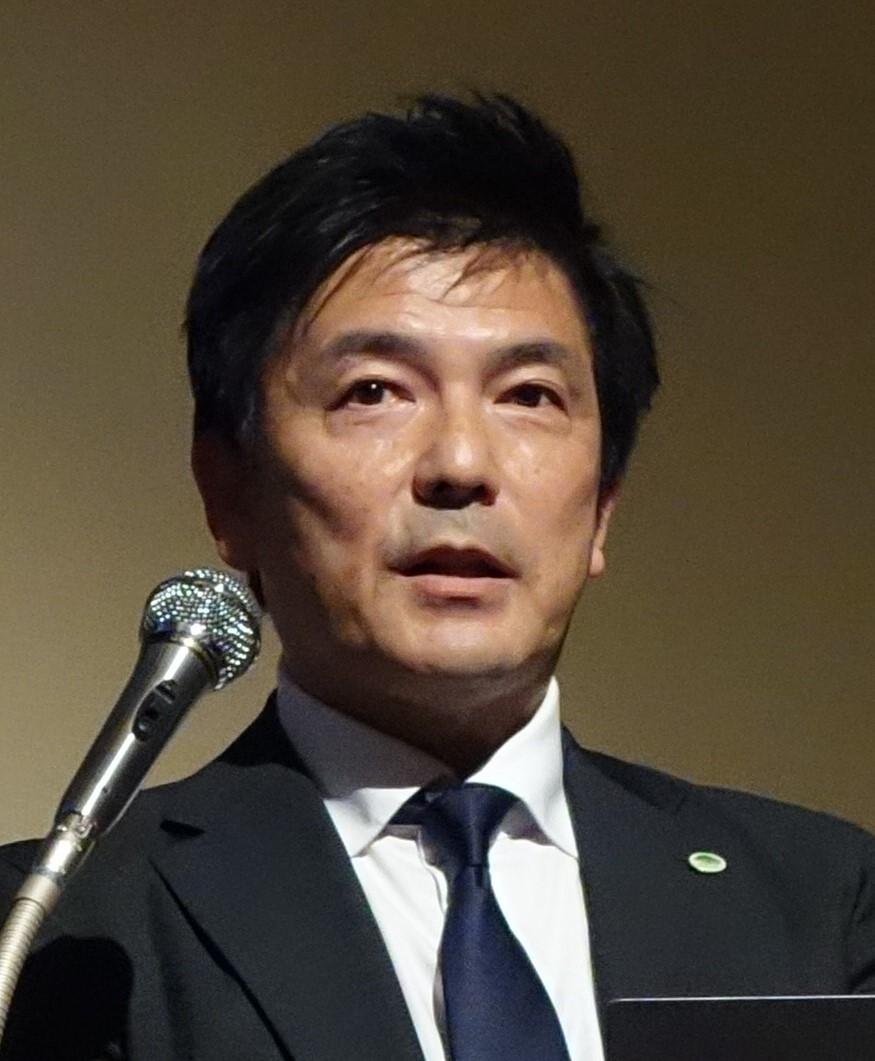
日立製作所 ひたち協創プロジェクト推進本部 本部長 佐野 豊 氏
日立市様と一緒に取り組んでいる共創プロジェクトについてお話しいたします。私たちは「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」という企業理念のもと、社会課題を解決する社会イノベーション事業を国内外で展開してきました。その集大成として、現在、創業の地である日立市とともに「サステナブルなまちづくり」に取り組み、さまざまな知見を生かして、人々の利便性や快適さを高めるためにデジタル技術を活用した社会である「ソサエティー5・0」を社会実装することを目指しています。
共創プロジェクトは、2023年12月21日に日立市と連携協定を締結して始まりました。現在は社会イノベーションの専門人材約100名を参画させ、事業を推進しています。具体例を三つ紹介いたします。まず「グリーン産業都市」です。日立市は脱炭素都市を目指し、50年までに280万トンの二酸化炭素(CO2)の削減を目標にしています。日立市内の弊社の大みか事業所では、デジタルを使ったCO2排出量の見える化などに取り組み、24年度にカーボンニュートラル達成を見込んでいます。このノウハウや仕掛けを共創プロジェクトでも活用し、地域の脱炭素化に取り組んでいます。
「デジタル健康・医療・介護」では、要支援・要介護者の方へのケアの質向上や、医療介護従事者の働き方改革を目指し、医療機関やご家族の間で情報を連携させる実証実験を24年9月に始めました。「公共交通のスマート化」では、交通や移動の活性化による街のにぎわいの創出と誰もが移動しやすい街を目指しています。
日本全体に目を向けると、人口や地域生産額割合について日立市と同じ特性を持つ都市は、国内で100以上あります。共創プロジェクトを通じて確立したソリューションや事業モデルを、ほかの地域にも展開することで社会イノベーションの加速を実践していきます。

