-
業種・地域から探す
続きの記事
茨城県産業
将来の飛躍に向けて挑戦を続ける茨城県産業界。原材料やエネルギー価格の高騰を受けて景気の先行きには不透明感が漂うものの、中長期的の経営基盤強化を見据えた人材育成や、新規事業創出を目指す取り組みが官民で着実に進展している。今回の「茨城県産業特集」では、大井川和彦茨城県知事のメッセージのほか、県内の企業立地動向、県内の国立大学の動向や大手企業の地域貢献などを10ページにわたり紹介する。
金融機関トップが語る 地元中小企業支援の取り組み
お客さまとの対話を重ね、経営課題の解決をサポート/
常陽銀行 秋野 哲也 頭取
-

秋野 哲也 頭取
茨城県経済は、生産活動や住宅投資など一部で弱めの動きがみられるものの、個人消費の増加や設備投資の持ち直しに加え、雇用・所得環境に改善の動きが続くなど、全体では緩やかに回復している。ただし、物価高や人手不足、金利上昇が企業や家計にもたらす影響、為替動向、不安定な海外経済動向の影響については引き続き注視する必要がある。
こうした中、お客さまとの対話を重ね、コンサルティング機能を発揮し、資金繰りの支援や設備投資ニーズに積極的に対応している。また、金利上昇が資金調達コストに影響を与える中で、固定金利による資金調達や既存のお借入れに対する金利リスクのヘッジ提案など、お客さまの財務の安定化に資する活動にも取り組んでいる。
さらに、当行が持つネットワーク・機能を活用し、仕入れ先や販路の拡大、生産性向上にむけたデジタル化・業務効率化、CO2排出量の測定・削減、従業員の福利厚生の充実等、多岐にわたる経営課題の解決をサポートしている。2025年は「団塊の世代」が75歳以上を迎え、後継者不足のさらなる深刻化が予想されることから、事業承継・事業転換へのサポートを一層強化したい。
当行は持続可能な地域社会の実現にむけて、地域の皆さまの課題に寄り添い、ともにあゆみ解決することで、新たな価値を創り続けていく。
地元中小企業を全力で支援/
筑波銀行 生田 雅彦 頭取
-

生田 雅彦 頭取
茨城県経済は、在庫調整の進展や受注環境の持ち直し等により製造業の業況が改善するとともに、サービス業においてもコスト上昇分を価格に転嫁する動きが広がり収益力の改善がみられる。一方、地元中小企業を取り巻く事業環境は原材料高や円安による仕入価格の上昇に加え、人材確保のための人件費の増加などコスト全般が高止まりしており、依然として厳しい環境にあると捉えている。また、日本銀行の政策金利の引上げにより過剰債務を抱える事業者の金利負担の増加も懸念される。
このような環境のなか、当行は計画の最終期を迎えた「第5次中期経営計画」の総仕上げに取り組んでいる。本計画では「地元中小企業の徹底的な支援」を重要施策に掲げ、資金繰り改善支援などの金融支援をはじめ、ビジネス交流商談会の開催による販路支援、広域ネットワークを活用した事業承継支援など、地元中小企業を支える取り組みを積極的に展開している。また、気候変動問題など、SDGs(国連の持続可能な開発目標)への対応を持続的な企業成長への重要課題として捉えるなか、社会的課題の解決を目指した「サステナブルファイナンス」にも積極的に取り組んでいる。
当行は、今後も「ファースト・コール・バンク」(最初に相談したい銀行)の実現を目指し、グループ一体となって企業価値を高め、豊かな社会づくりに貢献していく。
金利上昇の影響を受けているお取引先と深度ある対話/
茨城県信用組合 渡邉 武 理事長
-

渡邉 武 理事長
茨城県経済は、物価上昇の影響が見られるものの、雇用・所得環境の改善を背景として個人消費が緩やかに増加するなど、基調としては回復傾向にある。一方、中小・小規模事業者の皆さまは、仕入価格や人件費の高騰により利益が圧迫されており、厳しい経営環境が続いている。また、個人の皆さまについても、物価上昇による家計への影響が懸念される。
このような中、当組合は2022年にスタートした第10次中期経営計画(計画期間3年)に基づき、「笑顔と活力のある地域社会をお客さまと共に創る金融機関」を経営ビジョンに掲げ、お取引先への資金繰り支援や、販路拡大・経営改善・事業承継などの本業支援に取組んでいる。
資金繰り支援に関しては、金利上昇の影響を受けているお取引先を訪問し、業況を確認した上で、資金調達等についての深度ある対話を実施している。また、本業支援に関しては、お取引先の販路拡大を支援するため、JR東日本グループ各社や県内自治体と連携し、「金×鉄×官」による地域活性化策として、水戸駅改札前にて商品を販売・宣伝する「けんしんエキナカマルシェ」を開催している。
そのほかにも、フードドライブ活動や学生向けの金融教育など、社会的課題の解決につながる活動を実施しており、地域の皆さまと共に、地域の持続的な成長に貢献してまいりたい。
お客様の経営課題解決に尽力/
水戸信用金庫 飯村 次男 理事長
-
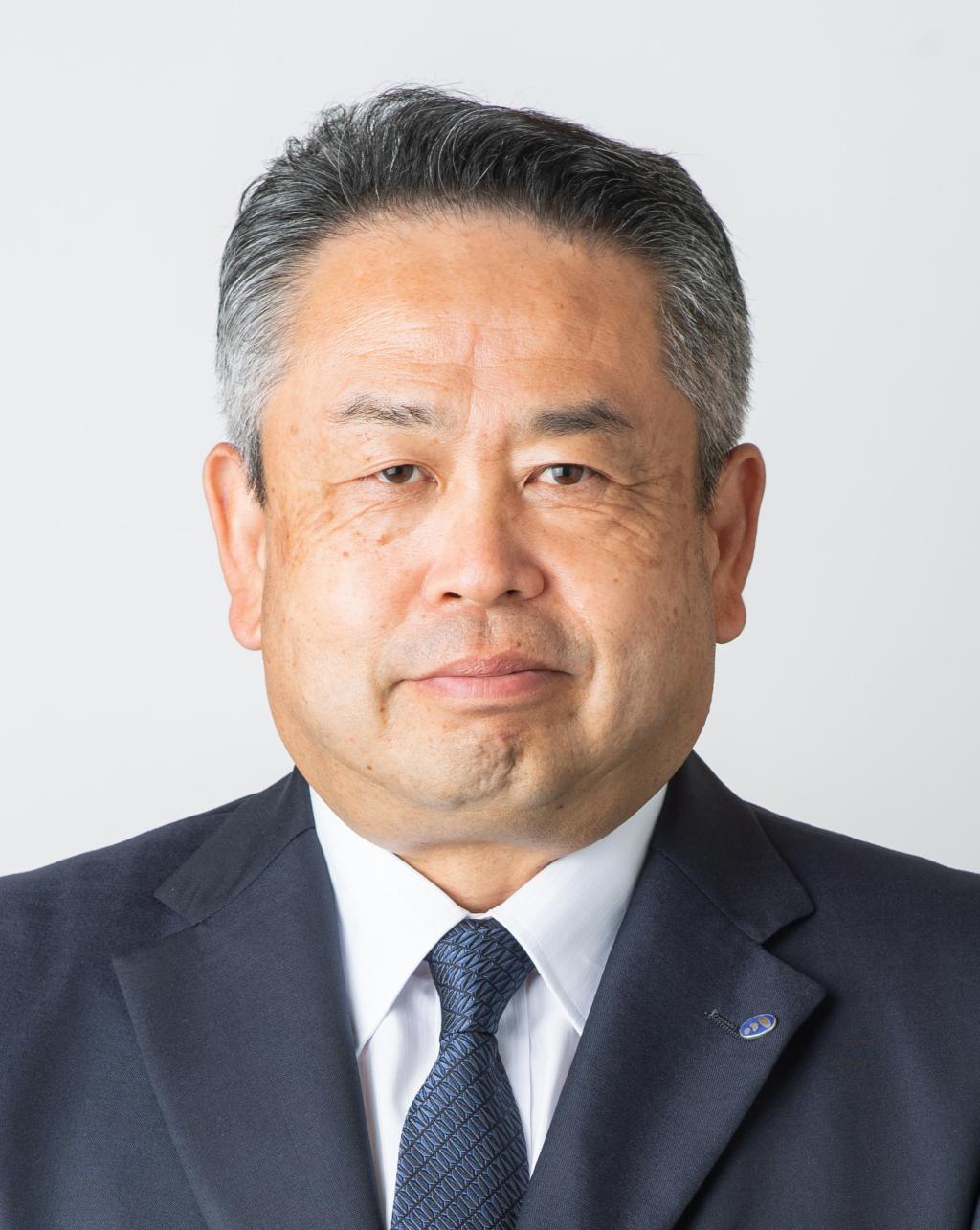
飯村 次男 理事長
茨城県経済は、生産活動など一進一退の状況にあるものの、設備投資や個人消費の持ち直しに加え企業収益に改善の見込みがあり、全体では持ち直ししている。
当金庫では、お客さまとの「対話」を通して事業に関するさまざまな課題を共有し、課題に応じて、全国254金庫の信用金庫ネットワーク等を活用した「販路拡大・販促情報支援」や補助金の情報および申請をサポートする「補助金申請支援」、外部専門機関等を活用した「経営改善支援」、「事業承継・M&A支援」等のサービスを提供し、事業の成長から次世代への事業承継までサポートしている。
そのような取組みのなかでも、県内経済の活性化に向けて力を入れているのが「創業支援」である。創業は、地域にとって経済を活性化し、雇用を生み出し、新たなイノベーションや地域が抱える問題解決の糸口となる可能性を秘めている。当金庫では日本政策金融公庫と連携し、勉強会や個別の相談対応、事業計画策定支援、事業者向けセミナーの共同開催等を行ってきたほか、創業支援協調融資「つなぐ」を積極的に提案している。また、インキュベーションオフィス「夢プラザ」を運営し創業を支援している。
今後もお客さまにとってもっとも身近な金融機関として、お客さま一人ひとりに寄り添い、地域経済の発展に貢献してまいりたい。
お客さまに寄り添った事業者支援/
結城信用金庫 石塚 清博 理事長
-

石塚 清博 理事長
当金庫の景気動向調査では、茨城県西地域の7―9月期の全業種の景気判断DIはマイナス9・3と、前回調査に比べ1・4ポイント低下し、景況感はわずかに悪化した。雇用面では人手不足感がやや緩和したものの、依然として売上の停滞・減少、原材料高等の問題を抱えており、地域中小企業の景気回復の実感は乏しいものになっている。
また、市場金利が上昇する中、今後の金利情勢についてお客さまは、期待と不安を抱えている。お客さまに寄り添った対応が強みである当金庫は、これからも地域・お客さまに寄り添った支援を重要課題として位置づけ、顧客訪問モニタリング活動を継続していく。その中で、多様化する経営課題に対し、全国254の信用金庫の業界ネットワークを活用しながら、地域を超えた事業者支援に取り組んでいく。
当金庫の経営方針は「小口先数主義」である。小口先数主義とは、お客さまとの接点を重視した営業活動から信頼関係を築き、蓄積した定性情報を基に、課題解決に取り組むものである。当金庫は今年122周年を迎えた。外的環境が大きく変化する中、当金庫は変えるべきものは変え、「地元ともに心はひとつ」という基本理念は変えずにきた。今後もこの精神を忘れることなく、一人ひとりのお客さまとしっかり向き合い、地域社会の発展を目指していく。
県内観光企業を積極的にサポートし、地域経済の未来を拓く/
商工組合中央金庫 水戸支店 新井 竜作 支店長
-

新井 竜作 支店長
県経済は一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している。今後力強く成長するためには牽引役の存在が重要である。
私はその牽引役の一つが観光産業だと考える。観光地の魅力を図るにはアクセスや施設、ホスピタリティ等様々な要素があるが、今後の成長可能性を見極めるにあたって、最も重要な指標は「その土地の歴史や文化」だと思う。
茨城県には偕楽園や大洗磯前神社、袋田の滝等、歴史や文化を感じられる建造物や名勝が非常に多い。
それらが纒うストーリーをわかりやすく伝えた上で、観光客に訪れたいと魅力に感じてもらうために皆が一丸となって磨き上げすれば、素晴らしい体験を提供できると確信している。
かくいう私も毎年夏は大洗、冬は袋田に旅行しているが、首都圏在住の家族や友人には大変好評である。
当金庫は「企業の未来を支えていく。日本を変化につよくする。」というパーパスを軸に、地域活性化の中心的な役割を果たす観光関連事業者との連携を強化している。
西行法師が日本三名瀑のひとつに数えられる袋田の滝を「四度の滝(四季に一度ずつ来るべき滝)」と評しているように、観光客が複数回しかも宿泊する形で訪れてもらえるように関連産業を積極的にサポートすることで、我々の存在価値を見出していきたい。
価格転嫁の進展による業績向上を支援/
日本政策金融公庫 水戸支店 福岡 和樹 支店長
-

福岡 和樹 支店長
日本公庫が実施している小企業の決算状況調査によれば、2023年度決算において、前年度と比べて売り上げが増加した企業の割合は、前回調査から上昇しているものの、採算が前年度から悪化した企業の割合は、改善した企業の割合を上回っている。
新型コロナウイルス感染症の5類移行や好調なインバウンド需要により、売り上げが増加したものの、仕入価格、人件費の上昇等により、収益を圧迫しているといえる。
なかには収益が改善していないにもかかわらず、従業員を確保するために賃上げを行った企業も少なくない。
増収増益企業をみると、仕入価格、人件費のいずれも半数以上の企業が価格転嫁できているのに対し、減収減益企業では、価格転嫁できている企業割合は増収増益企業より大幅に低いという実態がある。
価格転嫁の進展が業績向上の鍵となるが、当庫において、仕入価格等の高騰を受け価格転嫁に取組む方向けに、値上げを進める際のポイントを紹介した冊子、「上手な値上げの進め方」を刊行しており、特設サイト「日本公庫 事業者Support Plus」においては動画を掲載している。
事業者の皆様からのご融資、条件変更などのご相談に対し、資金繰り支援に対応するとともに、全国152支店のネットワークを活用し、地域の関係機関とも連携しながら、地域の課題解決に全力で取り組んでいく。
持続可能な農業の実現に向け 多様な担い手を支援/
JAバンク茨城県信連 八木岡 努 会長
-

八木岡 努 会長
近年、世界の食料・農業をめぐる状況は、世界人口の増加、世界的な異常気象、地政学的リスク等により、急激な情勢の変化や課題に直面している。これらは国内にも影響を与え、燃料・資材価格の高止まりや農作物の生産量・価格の不安定化など農業経営を逼迫させる事態となっている。
そのようななか、JAグループ茨城では、10月30日に「第30回茨城県JA大会」を開催し、向こう3ヵ年の基本方針を決議した。地域農業を途絶えさせず、持続可能な農業を実現するためには、多様な担い手による多様な農業に取り組む必要がある。具体的には、担い手の確保・育成をはじめ、環境に配慮した農業の展開、本県農畜産物の高付加価値化、食料安全保障強化に向けた対応などの課題に取り組んでいく。
これらの課題を解決するために、当会では農業担い手の抱える経営課題の解決に向けた「担い手コンサルティング」の展開や、ビジネスマッチングによる販路開拓などに取り組んでいる。
更に、今年度の新規事業として、茨城県みどりの食料システム基本計画に基づき県が取り組む「環境負荷低減事業活動実施計画の認定(いばらきみどり認定)」の取得農業者への利子補給を行うなど、農業者を直接支援している。
これらを通して、農業活動による地域の活性化に尽力してまいりたい。

