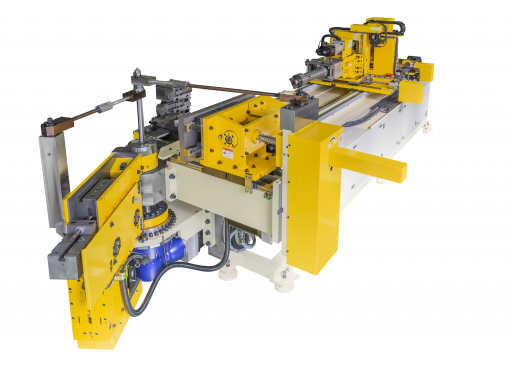-
業種・地域から探す
続きの記事
MF-TOKYO2025(2025年7月)
鍛圧機械に関する国際展示会「MF-TOKYO 2025 第8回プレス・板金・フォーミング展」が16日から19日までの4日間、東京・有明の東京ビッグサイト東展示棟4-8ホールで開かれる。主催は日本鍛圧機械工業会(日鍛工)と日刊工業新聞社。開場は10時から17時(19日は16時)まで。入場料は1000円(招待状持参者および事前登録者、中学生以下は無料)。
応用進むレーザー微細加工技術
【執筆】広島大学大学院 先進理工系科学研究科 教授 岡本 康寛
レーザー加工ではパワー密度、パルス幅、波長がプロセス形態を決定する重要な因子であり、それらを目的に応じて選択することで所望の加工を実現している。近年では短波長化や、短パルス化、高出力化が進み、熱影響の少ないアブレーション加工の産業応用が進展しつつある。除去・接合・成形の3大加工法を一つのツールで行えるレーザー微細加工は、デジタル技術との相性にも優れていることから、今後ますますの応用展開が期待される。
パワー密度選定 多様な加工実現
レーザー加工において単位面積当たりの出力であるパワー密度は重要な指標だ。それを変化させることで、例えば金属材料においては、1平方センチメートル当たり10キロワット程度だと形状変化を伴わない加熱のみ、同1メガワット程度だと溶融、さらに同10メガワットよりも大きくすると瞬間的に材料を蒸発させることが可能となる。このパワー密度は集光ビーム径を変化、すなわちレーザー光を空間的に制御することで管理できる。
またレーザー光の出力は連続的、もしくはオン・オフを繰り返すパルス的な手法に大別され、後者においてはレーザー光のエネルギー投入時間を決定するパルス幅が材料への熱影響に関係する因子である。一般にパルス幅が短いほど材料への熱影響を抑制でき、時間的な制御によって熱的作用を制御できる。
レーザー加工ではパワー密度とパルス幅を目的に応じて用いることにより、さまざまなアプリケーションを実現できる(図1)。パルス幅が長い領域では、温度変化により材料特性を制御する表面改質や、溶融現象を伴う溶接などに利用できる。そしてパルス幅が短く、パワー密度が大きくなるにつれて、材料の溶融に加え、蒸発現象を伴う切断、穴開けのプロセスが可能となる。さらにパルス幅が短く、パワー密度が大きくなると材料の蒸発現象が主体となる衝撃硬化(レーザーピーニング)にも活用できるようになる。
短波長・短パルス化によるアブレーション加工の普及
レーザー光のもう一つの特徴として波長があり、光吸収特性や加工形態によってレーザー光の波長を選定する。近年はレーザー光の短波長・短パルス化が進み、材料への熱影響を抑制した材料除去が期待できるアブレーション加工が身近なものとなってきた。そして高出力のパルスレーザー発振器が開発され、レーザーアブレーション加工の産業応用が進みつつある。
半導体業界で期待される樹脂やガラス材料の微細穴開け加工や、形状創成のための各種材料の3次元(3D)精密微細加工などの取り組みが進む。一般に10ピコ秒(ピコは1兆分の1)程度以下のパルス幅を出力できる超短パルスレーザーを用いると、材料への熱的影響を極めて小さくできる。さらに数百キロヘルツ単位で繰り返し出力されるパルスレーザー光を高速で走査できるシステムの開発もあいまって、3D精密微細レーザー加工は微細形彫り放電加工に匹敵するポテンシャルを示しつつある(リブ加工のような特殊な領域は難しい)。
応用技術多数 さらなる進化に期待
加えて、レーザー加工は図2に示すように3大加工法である除去・接合・成形を一つのツールで実現できることから、多くの応用技術がある。微細加工ではないが、除去加工としてはレーザー加工において大きな市場である板金分野で100キロワット級のレーザー発振器を搭載した装置が開発されるなど、プロセスの高速化が目覚ましい。
接合加工においても、パルスレーザーが高輝度連続発振レーザーに置き換えられて高速化が進むとともに、接合技術の1種である3Dプリンティングには多くのプレーヤーが集まってきており、今後の実用展開が期待されている。
熱応力や衝撃硬化を利用したレーザーによる成形加工もデジタル処理との相性がよく、工程管理の高度化につながることが期待できる。さらに近年では光を作る技術として、レーザー光強度分布制御について活発に議論されており、AI(人工知能)を活用したオンデマンド光強度分布制御による生産工程の高機能化など、魅力的な手法開発が進むものと考えられる。