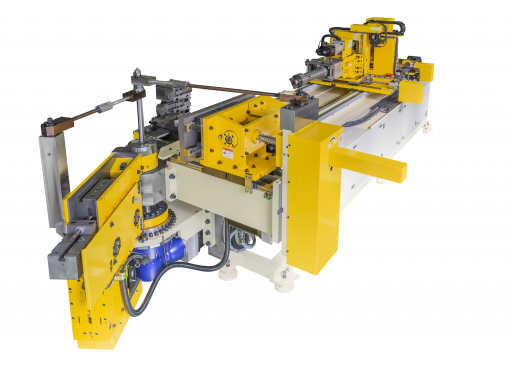-
業種・地域から探す
続きの記事
MF-TOKYO2025(2025年7月)
鍛圧機械に関する国際展示会「MF-TOKYO 2025 第8回プレス・板金・フォーミング展」が16日から19日までの4日間、東京・有明の東京ビッグサイト東展示棟4-8ホールで開かれる。主催は日本鍛圧機械工業会(日鍛工)と日刊工業新聞社。開場は10時から17時(19日は16時)まで。入場料は1000円(招待状持参者および事前登録者、中学生以下は無料)。
匠のプレス加工目指して 機械学習を活用した知能化スライドモーション制御
【執筆】 大阪産業技術研究所 加工成形研究部 主任研究員 四宮 徳章
製造業の人手不足に対応するため、筆者らは機械学習を活用したプレス加工の知能化に取り組んでいる。成形中のデータから不良を予測し、必要に応じて動作を自動で切り替えることで、不良率の低減と加工時間の短縮を実現した。また、強化学習を用いて鍛造条件を最適化し、製品の強度と生産効率の両立にも成功した。ここでは、熟練技能の再現と省力化を目指した新たな加工技術の可能性を紹介する。
プレス機知能化のねらい
プレス加工や鍛造をはじめとする製造業の現場では、近年、人材不足が問題になっている。特に2002年以降、全産業の就業者に対する製造業の就業者数の割合は低下を続け、02年には19・0%であったものが23年には15・6%まで低下している。この人材不足を打破する方法の一つとして、塑性加工の分野においてはAI(人工知能)の活用が進められている。AIを活用することで、加工条件の最適化や不良発見に要する作業時間を大幅に短縮することができる。
このような背景のもと、筆者らはサーボプレスなどスライドモーションをコントロールできるプレス機を、AIと組み合わせて活用することで、知能的なスライドモーション制御の実現に向け研究を進めている。図1に示すような知能的なスライドモーションは、いわば匠(たくみ)の技に相当し、状況に応じてたたき方を変えるという熟練技術をプレス機に搭載することを想定している。
畳み込みニューラルネットワークを用いたインパクト成形の不良率低減
①インパクト成形とその知能化について
インパクト成形は後方押し出し成形の一種で、薄い壁面を持つ容器成形に用いられている。容器成形として広く行われている深絞り成形と比較して、工程数が少なく、高速で成形できるため、近年、リチウムイオン電池(LiB)筐体(きょうたい)の成形方法として注目されている。
しかし、特に矩形(くけい)容器の成形では成形精度や成形不良の発生の面で課題がある。成形精度の向上や不良率の低減には、パルスモーションと呼ばれるスライドを上下に動作させながら成形するプレスモーションが有効であるが、このパルスモーションは成形に時間を要する。そこで、本研究では成形のきわめて初期のパンチの歪(ひず)み情報から、成形の良・不良を予測し(機械学習の分野では「推論」と言う)、成形不良が予測された場合、瞬時にパルスモーションに動作変更する知能化を検討した。
②畳み込みニューラルネットワークの利用
近年、画像認識においては畳み込み演算を用いたニューラルネットワークが推論精度の向上に大きな成果を上げている。
このアルゴリズムは空間的に近い情報の関連性を考慮したものになっている。
この空間的な情報の関連性を、センサーの時系列および空間的な配置情報の関連性として利用できると考え、学習に用いた。具体的には、4チャンネルのパンチ歪みの時系列データ65サンプリング分を、4×65画素の画像として、学習や推論に用いた。
③プレス機への実装と成形実験の結果
パンチの歪み情報から成形の良・不良を学習したモデルをプレス機に実装した。一般的なプレスモーションの場合、10回の成形で半数程度に不良が生じるような実験条件でトライを行った。成形不良と予測された場合に、パルスモーションに切り替える知能化プレス成形の検証を行った結果を図2に示す。
知能化プレス成形では、10個の成形品において割れ、しわ、大きな曲がりは確認されず、おおむね良好な結果となった。パルスの発動は10回の成形のうち4回あった。なお、パルス未発動時の成形時間が8秒なのに対して、パルス発動時の成形時間は29秒である。10回の成形がすべてパルスを用いた成形となると290秒かかるのに対して、知能化による選択的なパルス発動により、合計164秒の成形時間となった。知能化による選択的なパルス発動は、不良率を低減できるだけではなく、成形時間を大幅に短縮できるという結果を得た。
強化学習を用いた熱間鍛造条件の最適化
①リサイクル鋼(異形棒鋼)の熱間鍛造における課題
熱間鍛造では、被加工材の金属組成や鍛造温度、冷却速度によって成形品の強度が変化する。中でも、異形棒鋼を熱間鍛造した機械式定着鉄筋のようなリサイクル鋼の熱間鍛造では、鍛造後の熱処理は行わないことが一般的であるため、鍛造条件による強度の変化が非常に大きい。本研究では、成形品の強度安定と鍛造時間の短縮を目的に、強化学習を用いた熱間鍛造条件の最適化を試みた。
②強化学習を熱間鍛造へ適用
強化学習は機械学習の手法の一つであり、変化する環境の中で試行錯誤を通して最適な行動戦略を獲得していくための枠組みである。図3に、熱間鍛造条件の最適化に強化学習を用いた概要を示す。環境における状態を観測し、エージェントと呼ばれる部分が行動を選択する。適切な結果をもたらす行動には正の報酬(報酬)が与えられ、不適切な結果をもたらす行動には罰として負の報酬(罰)が与えられることで、最終的に最も高い報酬が得られる行動の選択を目的に学習する。
ここでは、金属組成に幅のあるリサイクル鋼を対象に、金属組成、鍛造温度、金型温度などを強化学習における「環境」、スライド速度や下死点停止時間などを「行動」、成形品の強度を「報酬」、プレス時間の長さ・鍛造荷重の大きさを「罰」として位置付け、強化学習を構築した結果について紹介する。なお、報酬については成形品強度に比例して報酬を与える「比例報酬」と、一定以上の成形品強度があれば同額の報酬を与える「定額報酬」として、実験を行った。
③強化学習のプレス機への実装結果
鍛造条件は鍛造温度、金型温度、被加工材の組成をランダムに設定した。強化学習を用いたスライドモーションにおいて、今回は比例報酬も定額報酬も①鍛造前の待機時間は0秒②スライド速度は毎秒5ミリメートル—という条件で鍛造を行ったため、違いの生じた下死点保持時間についての結果を示す。また、下死点保持時間の違いだけでは、鍛造荷重に影響を及ぼさないため、成形品強度と下死点保持時間の結果を示す(図4)。
下死点保持時間が0秒の場合、成形品強度が44・1キロニュートンだったのに対して、下死点保持時間2・5秒および比例報酬では46・1キロニュートンと、強度の高い成形品が得られた。また定額報酬においても成形品の強度は45・4キロニュートンと高い結果が得られた。
一方、下死点保持時間を比較すると、比例報酬では2・2秒の結果が得られ、同等の強度を持つ2・5秒よりも10%以上短いことがわかる。また定額報酬では1・1秒となり、2・5秒および比例報酬と比較して下死点保持時間を半減できた。つまり、比例報酬や定額報酬では成形品の強度の上昇と成形時間の短縮を両立でき、強度あるいは成形時間のどちらを重視するかを、実装する強化学習モデルの報酬の与え方で選択できた。
今後の展望
ここでは、機械学習を利用して成形中にスライドモーションを変更する知能化に関して解説した。学習に用いる教師データの自動収集や、機械学習ネットワーク構造の検討など、まだまだ改善の余地はある。またセンサー技術の向上やエッジAIの利用により、プレス加工への機械学習の適用拡大を期待したい。