-
業種・地域から探す
続きの記事
兵庫県播磨地区産業界
兵庫県の播磨地域にはモノづくりやエネルギー関連、地場産業など多様な企業が集積し、独自の技術とアイデアを生かした取り組みで、変化の早い時代のニーズに対応する。人手不足が叫ばれる中、SDGsの活動を進めることで、あらゆる課題解決に挑んでいる。播磨地域の企業の取り組みを紹介する。
「播磨」活躍企業の成長戦略①
伊東電機社長 伊東 徹弥 氏
-

伊東電機社長 伊東 徹弥 氏
物流施設や製造現場で、商品や製品を搬送・仕分けする物流システムやマテハン機器を手がける。独自技術のコンベヤー駆動用モーターローラー「MDR(パワーモーラ)」と独自ソフトウエアを駆使したMDR式マテハンシステムは、ラインの増設やレイアウト変更が容易な柔軟性・拡張性を備え、短工期で導入でき、省エネルギー型の「柔・拡・短・省」マテハンを特徴としている。
今後、「物流の2024年問題」の影響が本格的に現れることが予想される中、当社のマテハンで、仕分け作業の効率化や作業者の負担軽減など、運び方改革で働き方を改革し物流課題を抱える企業の一助になりたいと考えている。
国連の持続可能な開発目標(SDGs)の取組みにも注力する。当社の技術で社会のインフラとなる生産・物流業界を支え、社会の基盤づくりに貢献するほか、兵庫県内の地域と連携し、里山の整備を行っている。作業用ショベルカー向けに、樹木伐採用アタッチメントを独自開発し作業効率を高めるなど、モノづくり力を生かしている。微力ながら「山を守る、緑を守る」活動につながれば嬉しい。これを里山整備のモデル事業にしたい。
今後もオリジナル技術で「世のため人のためになるモノづくり」の理念をもって「先行開発」のスタイルで、新しいモノづくりにチャレンジし、社会に貢献する。
虹技社長 山本 幹雄 氏
-

虹技社長 山本 幹雄 氏
足元では、鋳物を扱う4事業が好調だ。競合の撤退や円安の影響でロール事業は伸びているほか、大型鋳物では受注残を抱えている。販売数量が減少傾向にある「デンスバー」も、価格転嫁に努めた効果が出てきた。小型鋳物事業も着実に成長してきた。2023年に大型鋳物事業部門とロール事業部門を統合し、素形材事業部としたことも鋳物事業の成長に寄与している。各事業部門の社員同士の交流が活発になり、モチベーション向上につながっていると実感する。
一方で環境エンジニアリング事業は、ゴミ焼却場建設の案件獲得に苦戦し、送風機事業も伸び悩んでいる状況だ。
今年1月にはアルミニウム合金を用いた高品質の鋳造品を手がける小口合金鋳造所を子会社化しグループの一員に加えた。現在は人材採用や育成など営業部門強化を進めている。同社の技術力を生かし、高品質なアルミ鋳造製品が求められる市場を開拓し、「虹技ブランド」の価値を高めていきたい。
脱炭素社会に向けた取り組みにも注力している。25年には西工場に700キロワット規模の太陽光発電を設置し、自家消費する仕組みを整える。2016年に開始した「虹の森」での森林整備のボランティア活動が今年、100回目を迎えた。今後も、さまざまな取り組みを通して地球環境の保護や改善に貢献していく。
仲田電機社長 仲田 五郎 氏
-

仲田電機社長 仲田 五郎 氏
当社は1958年の設立以来、自動車電装品向けをメインに多様な樹脂成形部品を幅広い分野へ提供してきた。強みは熱硬化性樹脂の加工技術だ。熱硬化性樹脂部品の製造は一般的に、高い技術力とコストが必要とされるため手がける企業が多くない。そのため取引先から〝欠かせない存在〟として高く評価されている。
多くの企業が生産現場での自動化を進めているが、当社では熱硬化性樹脂加工における省力化に向けた独自システムの開発にも注力。その一方で、作業者のノウハウと経験を生かした技術向上にも余念がない。
こうした取り組みが、厳しい寸法精度が求められる精密成形を可能にしており、最近では医療検査機器向け樹脂部品の引き合いも増えている。これに対応するために現在、工場拡張工事中であり、2025年7月末の完成を予定している。
新工場棟では、従来の熱硬化性エリアに加え医療機器関連エリアを新設する。今後見込まれる需要増に向け、生産体制の強化を図る。新規事業として医療検査機器向け樹脂部品の製造を事業のもう一つの柱に育てていく考えだ。
KLASS社長 頃安 雅樹 氏
-

KLASS社長 頃安 雅樹 氏
インテリア内装施工の自動壁紙糊付機やコンピューター式畳製造システム、オーダーメード産業機器を手がけている。
足元では、外食産業を始めとしたさまざまな産業で人手不足が加速し、製造業の国内回帰も進んだことで、自動化ニーズが本格的に高まってきた。産業機器のうち二次電池製造装置に関しては、継続した受注を獲得しており、当社の主力分野に成長しつつある。強みとする「職人技の自動化」技術を生かし、新エネルギー、環境、安全などの分野における幅広い需要に応えている。
インテリア事業では、内装施工省力化機器の開発や既存製品の新市場への展開を進めている。また創業以来の畳事業においては全国の畳店の存続・発展の支援が重要となる。畳店が営業活動や職人技を必要とする作業に専念できるよう、当社のコンピューター式畳製造システムなどの省人化提案を推進し、事業成長につなげる。今年10月には、「ソリューション&ネットワーク事業部」を立ち上げた。メーカーとして培ってきた技術力や顧客ネットワークなどの無形の経営資源を活用して、ソフトウエア・サービス提供にも力を入れる。既存部門との相乗効果で新たなビジネスを生み出していきたい。
KAJIWARA社長 梶原 敏樹 氏
-

KAJIWARA社長 梶原 敏樹 氏
発電所や工場、ゴミ焼却場などで用いられる粉じんや有害物質を除去する集じん機や脱臭装置といった環境機器の製造・販売を得意としている。
2024年の創業110年に向けて、さまざまな取り組みを進めてきた。昨年には新本社・新工場を竣工し、今年10月には、梶原鉄工所から「KAJIWARA」に社名変更するなど、まさに第二創業期を迎えている。部門や業種、年齢の差を越えて、全社員で魅力ある会社づくりに取り組んでいきたい。
足元では、脱炭素対応が各業界で本格化し始め、環境機器の引き合いは増えており、25年以降も需要は伸びる見込みだ。また22年に立ち上げた工事部が実績を積み上げてきたことで、装置メンテナンスの大型案件も受注できるようになってきた。今後も、装置製造からアフターサービスまで一気通貫で対応する強みを生かしたモノづくりに注力する。
ゴミ焼却場や下水処理場、地熱発電施設などにおいても、脱炭素化に向けた動きが始まっている。当社が手がける廃熱を利用した有機ランキンサイクル(ORC)発電システムも引き合いが増えており、ORC発電システムの積極的な提案活動を通して事業成長につなげていく。
赤穂化成社長 池上 良成 氏
-
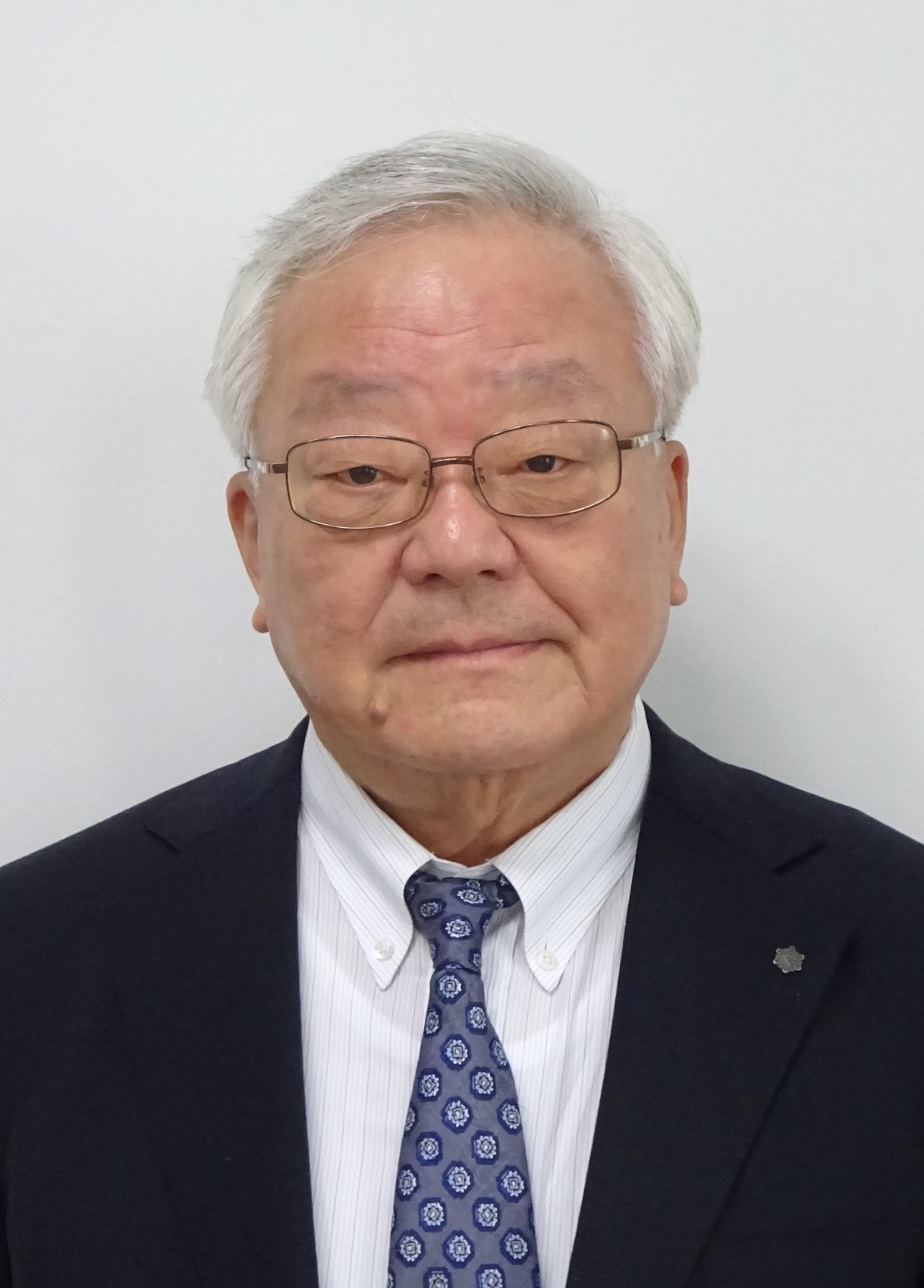
赤穂化成社長 池上 良成 氏
2026年に祖業400年を迎える赤穂化成は、塩づくりの技術を生かして幅広い事業を展開するミネラルの総合メーカー。無機塩類製品を製造する化成品事業や機能材事業、食塩を手がける調味事業などを展開している。
経営環境は全事業が順調に成長している状況だ。化成品事業では人工透析メーカーが増産に動き、販売する塩化マグネシウムなど原薬が伸びる見込み。入浴剤も物価高の影響の中でも需要が増加している。25年には、人工透析向け原薬の供給体制の強化を目的とした新工場の完成・稼働を予定している。市場ニーズをいち早く掴み、需要に応える生産体制を整えて事業成長につなげたい。
今年は地震や猛暑の影響で保存水や熱中症対策飲料のニーズが高まった。深層水や塩を生産する事業所は高知県にあり、南海トラフ地震対策の必要性を感じた年でもあった。災害時に必要とされる商品を安定供給できるように、兵庫県赤穂市の本社を含めた新たな組織体制の構築を進める。
赤穂市の主要施設のネーミングライツ(命名権)取得や、社員が各料理に適した塩や調理法を研究・調査する「塩味ソムリエ制度」を社員を対象に立ち上げる計画で、地域と会社を盛り上げて祖業400年に向けて邁進(まいしん)する。

