-
業種・地域から探す
続きの記事
エネルギー産業
電源構成 主軸に脱炭素電源/水素 社会実装加速
2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、初めて再生可能エネルギーが最大電源に位置付けられた。原子力も活用する方針で、脱炭素電源に主軸を置くことが明示された。S+3E(安全性+安定供給・経済性・環境)の原則は維持。特定の電源や燃料源に過度に依存しないバランスの取れた電源構成を目指しつつ、脱炭素効果の高い電源を安定的に確保できる地域への産業集積などを促し、グリーン・トランスフォーメーション(GX)実現を目指す。
第7次エネ計画/再生エネ・原子力軸に
世界的に気候変動対策と産業政策を連動させエネルギー転換を産業競争力につなげる政策が打ち出される中、日本では第7次エネ計画が脱炭素化に向けたGX戦略の「GX2040ビジョン」と一体的に示された。
日本のエネルギー環境は第6次エネ計画策定時とは大きく変化した。ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルのイラン攻撃で緊張が高まる中東情勢に加え、AI(人工知能)の普及に伴い、省エネルギー対策や人口減で減少が見込まれた電力需要が、中長期的に急拡大する見通しに修正された。経済安全保障の観点からエネルギーの安定供給を確保することが急務となった。
第7次エネ計画では40年度の電源構成を再生エネ4—5割程度、火力3—4割程度、原子力2割程度とした。原発は東日本大震災以降の「可能な限り原発依存を低減する」という表現を削除、脱炭素電源として最大限活用。廃炉が決まった原発の次世代革新炉への建て替え要件も緩和する。再生エネと原子力に軸足を置くことで、23年度に15%だったエネルギー自給率が40年度に3—4割に引き上がる見通しだ。
最大電源に位置付けられた再生エネは、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促す。国産の再生エネの普及拡大と、技術自給率の向上を図ることは産業競争力の強化にもつながる。日本発のペロブスカイト太陽電池や、浮体式洋上風力などの開発・実用化が期待されている。
-

ペロブスカイト太陽電池は社会実装を目指す動きが加速している(NTTデータによる高層ビル壁面での実証実験=24年12月)
ペロブスカイト太陽電池は40年までに約2000万キロワットを導入する目標が掲げられ、社会実装を目指す動きが加速している。洋上風力発電については40年までに3000万キロ—4500万キロワットの案件を形成する目標を掲げた。また次世代地熱発電技術を30年代に実用化することを目指し、研究開発や実証などを促していく。
火力は安定供給に必要な発電量を維持しつつ、低炭素な液化天然ガス(LNG)火力を確保し、排出された二酸化炭素(CO2)を地中・海底下に貯留するCCS事業や、火力発電での水素・アンモニア混焼などの対策も合わせて脱炭素化を進める。
脱炭素—カギ握る水素
脱炭素社会の実現に向けて、カギとなるエネルギーが水素。世界で水素の需要が拡大しており、各国の水素産業に対する支援も、技術開発から社会実装へと移行しつつある。日本でも24年10月、水素の社会実装を強力に推進する「水素社会推進法」が施行された。
水素は使用してもCO2を排出しないエネルギーだが、製造の際に化石燃料が使われる場合がある。同法では「低炭素水素等」を定義。水素を製造する際に排出されるCO2の量が一定以下、または「水素等」に含まれる合成燃料などの利用が日本のCO2削減に寄与するものであることが定められた。
国内の再生エネを利用して作ることもできるため、エネルギー自給率の向上にもつながる。政府は水素等製造事業者の事業計画を認定して資金補助などを行うほか、既存の燃料に比べ割高な水素価格に対する値差支援を行う。液化やアンモニア製造の設備、貯蔵タンク・輸送パイプラインなどのインフラの整備に関しても資金援助が行われる。
-

都営バス営業所(東京都江東区)に3月開設した「岩谷コスモ水素ステーション有明自動車営業所」(岩谷産業提供)
また水素普及の推進役として、水素利用量が多く充填時間が短い燃料電池(FC)商用車の社会実装支援を加速する。5月には需要を率先して喚起する「重点地域」に東北、関東、中部、近畿、九州の5地域と福島県、東京都、神奈川県、愛知県、兵庫県、福岡県の6都県を選定した。重点地域ではディーゼル燃料との差額の約4分の3に当たる1キログラム当たり約700円を国が追加支援し、民間事業者の負担を軽減する。
今田美桜さん 新CM 「エネバランス」の大切さ—優しく伝える/電事連
電気事業連合会が俳優の今田美桜さんを起用した新しいコマーシャル(CM)の放映を始めた。今後、国内の電力需要が増え、原子力や脱炭素火力などとのエネルギーバランスが重要になることを今田さんの持つ優しいイメージで訴えている。
-

今田美桜さんを起用した新しいCM
各30秒で2バージョンあり、まず「電気とひとの物語・冷蔵庫あけたら」編は、仕事を終え帰宅した一人暮らしの女性が冷蔵庫を開けて物思いにふけるストーリー。冷蔵庫の中にあるはずのない両親の手づくりプリンが—。そこから幼い頃、実家の冷蔵庫のプリンを楽しみにしていた思い出に浸りつつ「電気に流れているのは、ひとの気持ちなのかもしれないな」と、実家の両親のやさしさやぬくもりを実感する。メッセージ性の強いバージョンだ。
もう一つの「電気とひとの物語・この撮影も」編は、「冷蔵庫あけたら」編の撮影場面から始まる。撮影終了後、役柄から今田さん本人に戻り、照明やカメラ、モニターなど機材が並ぶ現場を見回しながら「もしも電気がなかったら、この撮影もできないんだよね」とつぶやく。続けて電事連から、安全性の確保を大前提に再生可能エネルギーと原子力を最大限活用しつつ、火力の脱炭素化にも取り組み、各電源のバランスを図っていくという説明が流れる。
今田さん出演の新しい動画はほかにも電事連ホームページで「伝えるのは今だ・エネルギーミックス」編と「同・ヒートポンプ」編が見られる。それぞれ90秒の長編。今田さんが刑事に扮(ふん)し、事件現場でエネルギーミックスの重要性やヒートポンプの環境性能について詳しく解説しながら、事件を解決へ導くストーリー。最後に今田さんが「エネルギーのこと、知ってほしいのは今だから。」と名前に引っ掛けた締め言葉で電事連のメッセージを発している。
ペロブスカイト太陽電池 技術解説/政府・メーカー動向 日刊工業新聞社
-
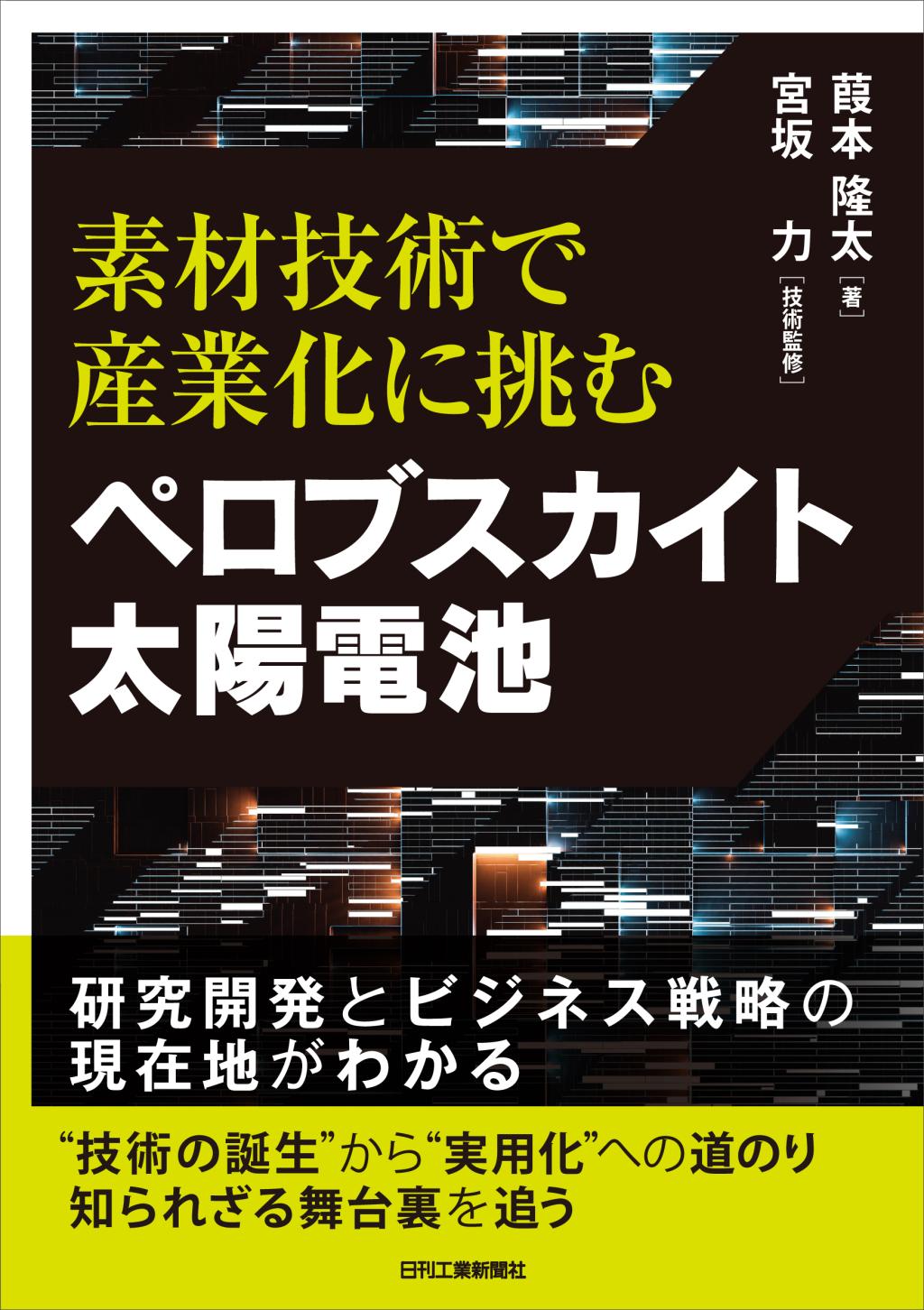
素材技術で産業化に挑む ペロブスカイト太陽電池
日刊工業新聞社では次世代型太陽電池の本命とされる「ペロブスカイト太陽電池」の書籍を販売。ペロブスカイトは薄くて軽く曲げられる太陽電池で、脱炭素化へのカギを握る日本発の技術。同書ではこの技術の仕組みや構造を解説しつつ、完成品メーカーや政府の動きのほか、日本の強みとなる素材技術に焦点をあてて関連企業の取り組みも探っている。同技術の誕生ドキュメントも収録。
太陽電池ディスカッション 7月16日/インテックス大阪 未来モノづくり国際EXPO
これに関連して、7月16日15時から大阪市住之江区のインテックス大阪6号館「未来モノづくり国際EXPO」ステージで、同書の技術監修をした桐蔭横浜大学医用工学部の宮坂力特任教授がペロブスカイト太陽電池ディスカッション「実用化加速へ!産学が語るペロブスカイト太陽電池の課題と展望」に登壇する。聴講は無料。申し込みは未来モノづくり国際EXPO公式ホームページ(fmiexpo.nikkan.co.jp/)へ。

