-
業種・地域から探す
続きの記事
さいたま市
立地・産業振興に優れる政令市
中小企業を支援・住み続けたい街
さいたま市は2001年に浦和・大宮・与野の3市が合併して誕生した。03年には政令指定都市に移行。05年には岩槻市と合併した。現在の人口は約135万人。交通の要衝として新幹線を含む鉄道網や道路網が整備されている。都心に近い立地で産業振興にも優れ、住み続けたい街としても知られる。さいたま市を含めた埼玉県を地盤とする大栄不動産の石村等社長と、さいたま市産業創造財団の中村雅範理事長に、さいたま市の街づくりや市内中小企業支援策などについて聞いた。
未来の街づくり 官民連携 重要/大栄不動産 社長 石村 等 氏
-

大栄不動産 社長 石村 等 氏 -

「大宮門街」は一部店舗をリニューアル
―さいたま市の立地優位性をどう見ていますか。
「歴史的に見ると中山道の浦和宿と大宮宿があり、交通の要衝であることが第一にあげられる。現在は行政と文教地区が中心の浦和、交通の利便性に優れ商業の集積度が高い大宮、大宮操車場跡地のさいたま新都心の三つのエリアで市の中心が構成されている。さらに当社も応援企業として登録している埼玉版スーパー・シティプロジェクトの中で、美園地区は市のスマートシティさいたまモデルに位置づけられている」
―教育や住環境も含めた住みやすさでも評価されています。
「住みたい街ランキングで大宮は、横浜に次いで2位になるなど常に上位にある。市民意識調査でも住みやすいと思う人が86%、住み続けたいと思う人も87%という結果が出ている。特に0歳から14歳までの転入超過数は23年まで9年連続で全国1位だった。首都圏の居住空間の中で魅力と利便性を兼ね備えている点が高く評価されている。一方でマクロ的に見た場合、高齢化が進み人口が減少期に入った時に備えて未来の街づくりをどう進めていくかは、行政も産業界などと連携して一緒に考えていく必要が出てくるのではないか」
―産業分野では。
「市内の事業所数も市内で従事する従業員数も10年ほど前と比較すると着実に増えている。特に卸や小売り、飲食や宿泊など都市型の産業が多い。埼玉県内で創業して全国レベルの企業に成長した企業もある。県内に本社や拠点を移したり、東日本の統括機能を持たせたりする企業もある。交通の利便性が高く、雇用も比較的確保しやすい条件がそろっている。オフィスの稼働率や賃料を見ると、横浜よりさいたま市の方が高い傾向にある」
―大栄不動産のオフィスや商業施設の動向は。
「当社は市内に11のオフィスビルと五つの商業施設を所有しており、床面積の合計は約3万7500平方メートル超。うち稼働率は11棟が100%。残りも9割と高稼働の状況にある」
―大栄不動産などが大宮駅東口に開業した「大宮門街(かどまち)」は、一部の店舗をリニューアルしています。
「コメダ珈琲店の和の喫茶店『おかげ庵』と新業態のおむすび専門店『米屋の太郎』、春雨スープの『七宝麻辣湯(チーパオマーラータン)』はいずれも埼玉初出店。100円ショップの『セリア』も入る。街づくり全体や門街のにぎわいを重視して個性あるテナントを誘致した」
―今後の方針は。
「市が進めている産業集積拠点への企業誘致のほか、オフィスや住宅の供給なども含め、当社がさいたま市に貢献できる分野は多いと認識している。引き続き地域との関係を深めていきたい」
来年度、中堅企業の支援を強化/さいたま市産業創造財団 理事長 中村 雅範 氏
-
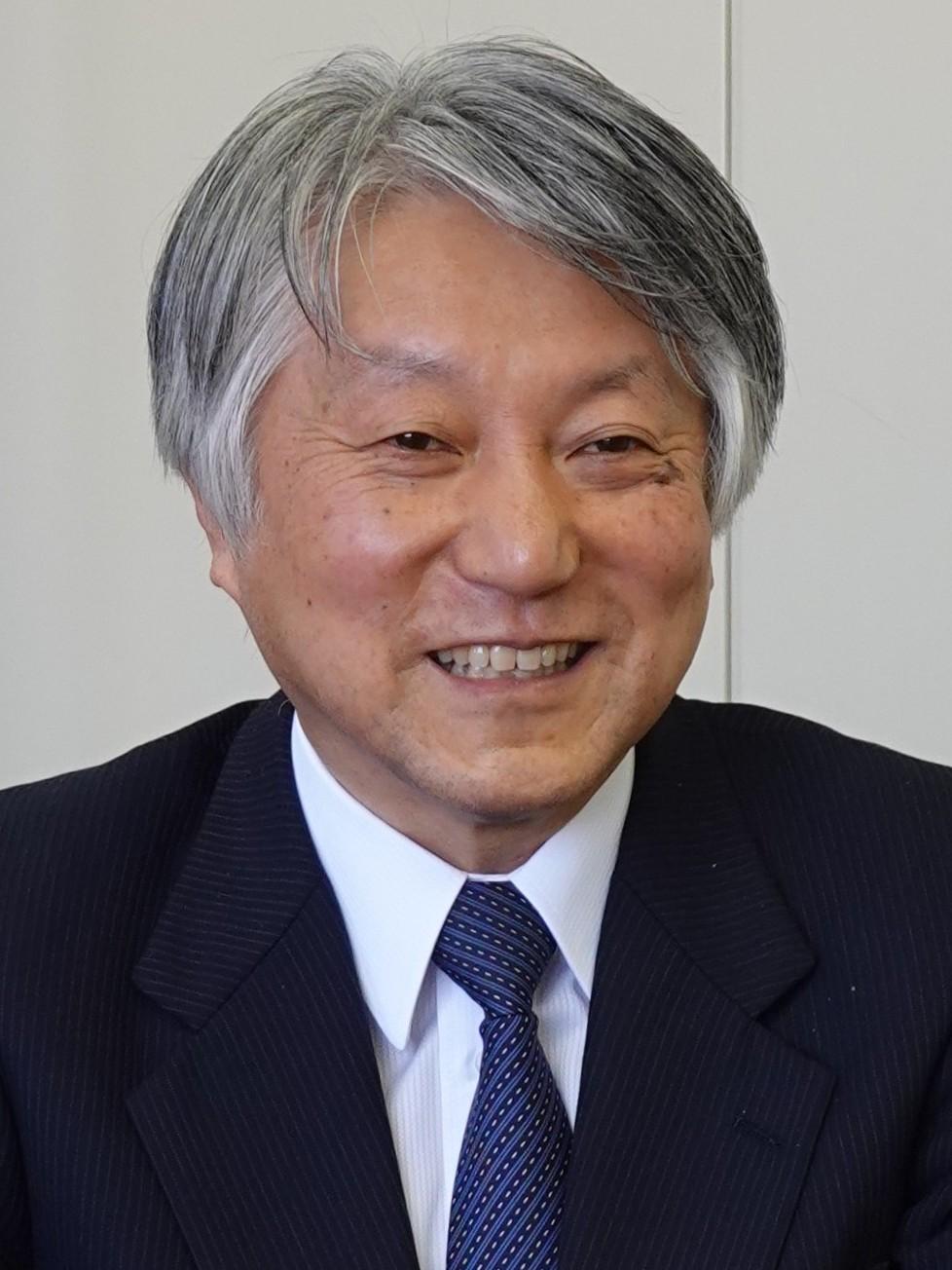
さいたま市産業創造財団 理事長 中村 雅範 氏 -

中小企業とドイツ企業の共同研究を支援
―さいたま市産業創造財団の特徴と役割は。
「市内の中小企業の成長を支援するため、04年にさいたま市が設立した。大学や大手企業、東日本エリアの企業とのマッチングを支援する『オープンイノベーション』や、製品開発や事業経営を担う高度人材などを育成する『人材育成支援』を実施している。さらに創業や金融に関する相談を受け付ける『創業・経営基盤強化支援』、従業員の福利厚生の充実を目指す『福利厚生支援』など、幅広い分野で企業をサポートしている」
―企業の成長に必要なことは。
「技術革新が加速する中、企業はデジタル変革(DX)やAI(人工知能)などの新技術を活用して、いかに成長に結びつけるかがカギとなる。企業が単独で課題を解決することが難しい場合には、他社との連携も必要となる」
―成長をどう支援しますか。
「オープンイノベーションと人材育成支援に力を入れる方針だ。オープンイノベーションは大きく三種類の支援がある。まずはニーズに応じて企業同士をマッチングする『産産連携』。次に、先進的な技術支援が必要な際に大学や研究機関に結びつける『産学連携』。最後が、新ビジネス開始に向けて新たな発想や知見を得るための『海外連携』だ。当財団が持つネットワークを最大限生かしていく」
「人材育成支援は大学やそれぞれの分野の専門家と連携して実施していく。高度経営人材や高度技術人材のほか、海外人材を育成する。海外人材は語学の面だけでなく、ビジネスの習慣や価値観などを備えた人材を育てる」
―価格転嫁推進も重要な経営課題です。
「原材料やエネルギー価格が高騰し、特に中小企業は厳しい局面に立っており、価格転嫁が非常に重要となっている。だが、製造原価が高騰したから製品価格を上げるということだけでは、利益の拡大に結びつかない。当財団では製品自体の付加価値を高めて顧客も納得した上で価格を引き上げる『製品の高付加価値化』を目指すことも支援している」
―中堅企業の支援にも力を入れています。
「さいたま市は25年度から中堅企業支援と、中堅企業への規模拡大を目指す中小企業への支援を進める方針だ。当財団がその実行部隊となる。専門家が企業を訪問して経営課題や今後の成長戦略をヒアリングする。新事業創出や海外展開、人材確保など企業ニーズを聞き、それぞれの企業の成長につながる支援を進めていく計画だ。中堅と、中堅へのステップアップを目指す中小支援を強化して経済の活性化にもつなげたい」

