-
業種・地域から探す
続きの記事
さいたま市
さいたま市 未来技術で躍動
東日本の中枢・上質な生活都市へ
埼玉県の県庁所在地さいたま市は2024年に人口135万人を突破した。「東日本の中枢都市」「上質な生活都市」を将来像に掲げる。25年度の予算で市は「激動する新時代に『未来技術』で躍動する地域産業づくり」に取り組む。清水勇人市長は「市内企業の業務効率化と付加価値向上支援を両面で実施する」と話すとともに、さいたま商工会議所の池田一義会頭は「今後も地道な活動を進め、価格転嫁の浸透に取り組んでいく」と語り、地元産業の活性化を積極的に推進する。
さいたま市長 清水 勇人 氏/業務効率化と付加価値向上 両面支援
-
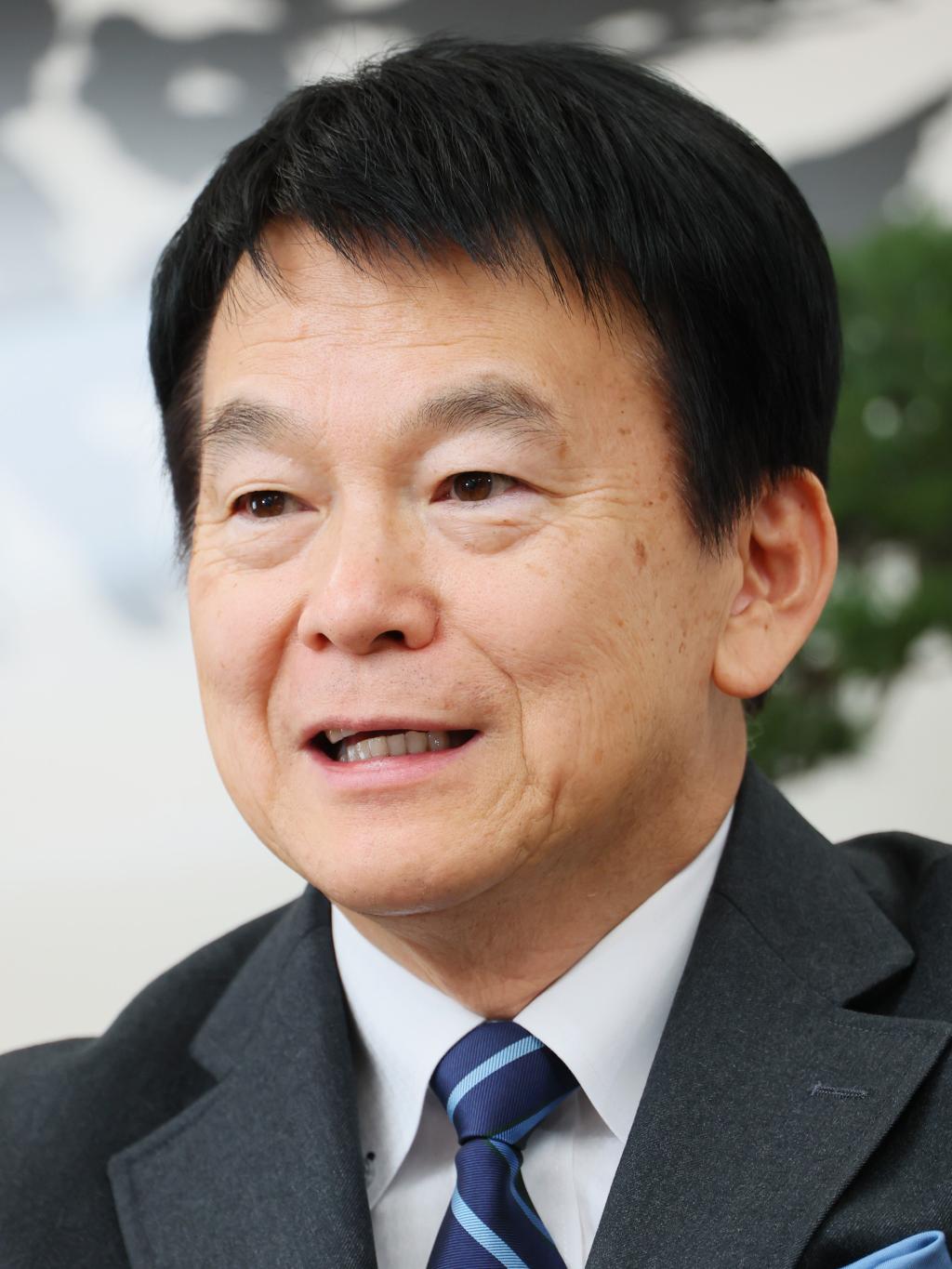
さいたま市長 清水 勇人 氏
―25年度予算案で中小企業の成長支援策は。
「物価高騰などの先行きが不透明な社会情勢でも中小企業が持続的に発展することを促すため、市内企業の業務効率化支援と付加価値向上支援を両面で実施する。DX推進支援によりデジタル化を進めて業務効率を向上させるとともに、ブランディング支援やGX推進支援、オープンイノベーションの推進による新商品・新サービス開発支援などで企業の付加価値向上を図る」
―デジタル地域通貨については。
「デジタル地域通貨機能を搭載した『さいたま市みんなのアプリ』の普及促進に加え、アプリの機能を向上して各行政サービスとの連携推進を図る。地域経済の活性化に向け、アプリを通じた市民生活支援や各種キャンペーンなどに要する経費補助のほか、市内事業者・加盟店などへの支援として、加盟店手数料を補助する」
―産業集積拠点の新たな候補地について。
「既存候補地6地区のうち5地区で事業着手や着手に向けた動きがある。高い企業立地のニーズの要望に応えるべく、今年度に見沼区の丸ケ崎地区など4地区を選定した。来年度、具体的な事業範囲や整備手法などの整理を予定している」
―リーディングエッジ企業認証制度の現状と今後については。
「24年度は新規で認証された日本製衡所を含む14社を認証しており、25年1月1日現在の認証企業数は34社。来年度以降の取り組みでは、理工系大学や高等専門学校との連携による支援の充実を検討するとともに、次世代を担うリーダーの育成研修など人材育成支援などにも取り組む」
―SDGs企業認証制度では。
「24年12月時点で294社が認証されており、24年度中には50社が新たに認証されている。今後は産学官金などとのパートナーシップ構築を推進することで、SDGsの取り組みを加速化させていきたい」
―大宮駅グランドセントラルステーション化構想の今後は。
「東日本の対流拠点としての都市機能や公共空間について、駅前街区の地権者や鉄道事業者、市民、企業などから聴取した意見を踏まえ、現在の計画を補強することにした。25年度は意見や工事費高騰など社会経済情勢を踏まえたプランの更新作業を進める」
―新市庁舎計画の今後について。
「25年度は基本性能やデザイン、市民広場を含めた配置などの検討を深める。市民参加型ワークショップも開く。10月には中間報告を取りまとめ、パブリック・コメントを実施し、26年4月の基本設計図書完成に向けて検討を進める」
―分棟型の民間機能整備は。
「オフィス、商業店舗、宿泊施設をベースに検討している。サウンディング型市場調査で多様な業種の事業者から具体的な質問も多く寄せられ、前向きに検討する意欲があることを確認できた。公募条件などの検討をさらに進め、本庁舎やまちを訪れる人に喜んでもらえる機能の導入を目指していく」
さいたま商工会議所会頭 池田 一義 氏/価格転嫁の浸透へ地道な活動続ける
-

さいたま商工会議所会頭 池田 一義 氏
―さいたま市内会員企業の景況感と25年度の見通しは。
「直近のアンケートでは売上高が前期比増になると回答した企業が4割、利益も3割が増えると答えており、堅調な事業者が多い。製造業はあまり良くないが、消費が押し上げている」
―日本全体の今年の見通しは。
「それほど悪くはならないが、低空飛行は続くのではないか。特に中小企業にとっては厳しい。原材料価格の高騰に加えてエネルギー価格も政府による補助が終わり、物流業界などへの影響が大きい。価格転嫁もまだまだ進める必要がある。転嫁できているのは人件費以外の部分で、売り上げは伸びても利益増に結びつかない状況が続いている」
―商工会議所として25年度の取り組みは。
「第6次中期ビジョンの2年目に入る。構造転換が進む中で大きなターニングポイントを迎える。キーワードは『自己変革』。会議所を通じてさまざまな制度を活用してもらうことも後押しする。下請法改正の動きなども注目される」
―企業自らが稼ぐ力を高めるには。
「やはり『両利きの経営』という考え方が大事だ。まずは本業を磨いて深掘りする。さらに必要なのは『探索』。新たなものにチャレンジして製品やサービスを開発する。ニーズを作り出す。こうした取り組みを進めないと限界を迎える」
―具体的には。
「まず商工会議所として制度融資や補助金などの活用を後押しする。さらに将来のマーケットを見据えた時に海外展開は重要。日本貿易振興機構(JETRO)などの協力を得ながら国外への販路開拓も支援する。また社内の生産性向上にはデジタル変革(DX)が不可欠。デジタル化を通じた自動化や効率化を進める。これにより間接部門を効率化して営業や開発などに人材を振り向ける。人材採用や活用も大切。大企業と中小企業の賃金格差が拡大する中で、この差をどう埋めるかが課題になる」
―埼玉県商工会議所連合会と埼玉県商工会連合会は、タイミーと包括連携協定を結びました。
「タイミーの登録者は1000万人。それだけ働きたい人がいる。両連合会の会員1万1000社とどうマッチングしていくかが重要だ。一方で外国人材の活用なども支援していきたい」
―埼玉県は価格転嫁で先進的な取り組みを進めています。
「価格転嫁は県内だけで完結できる問題ではなく、全国的に広げていく必要がある。評価が高い埼玉県の価格転嫁支援ツールは、既に31の道府県のホームページでも紹介されており、2月にはUI(ユーザーインターフェース)の改善と、労務費データや男女間賃金格差データなどの追加アップデートが行われた。金融機関と連携した価格転嫁サポーターでは、功績が顕著なサポーターを大野埼玉県知事が表彰する表彰式も2月に行われた。好事例をさまざまな形で横展開する動きもある。今後もこうした地道な活動を進めていくことで、価格転嫁の浸透に取り組んでいく」

