-
業種・地域から探す
続きの記事
ロボットテクノロジージャパン(2024年7月)
産業用ロボットと自動化システムの専門展「ロボットテクノロジージャパン(RTJ)2024」が、7月4日から6日までの3日間、愛知県国際展示場(愛知県常滑市)で開かれる。今回のテーマは「アイデアは現場だけでは生まれない。#1パーセントのひらめき」。人手不足や生産性の向上が社会課題となる中、出展各社が自動化を実現する最新技術やサービス、システムなどを披露する。主催はニュースダイジェスト社(名古屋市千種区、樋口八郎社長)で、愛知県機械工具商業協同組合(同熱田区、水谷隆彦理事長)が共催する。
多彩なセミナーを開催、企画展示も充実
ロボの性能に触れて学べる 8つのシステムを体験
-

従来よりも高度なコースでロボと対決できる
RTJでは毎回、来場者が実際に産業用ロボットに触れることで、理解を深め、安全性や扱いやすさなどを感じてもらうための取り組みを実施している。主催者企画展示「産業用ロボット体験ゾーン」では協働ロボとのゲーム形式の対戦や、ロボに動作を指示するティーチングの体験ができる。日本ロボットシステムインテグレータ協会(SIer協会)、中部地域SIer連携会、次世代ロボットエンジニア支援機構が協力し、八つのコーナーを設ける。
SIer協会は、三明機工(静岡市清水区)が開発したシミュレーション上でロボのティーチングができる実習支援システム「デジタルトレーナー」を出展する。工場自動化(FA)シミュレーターを使って実機と同じ状況をシミュレーション上に再現。ロボに動きを教え込むための機材「ティーチングペンダント」で操作でき、ロボを購入しなくても実践に近い感覚で操作実習ができるため、技術者の育成に役立つ。
得意分野生かしたコーナー
-

前回展ではボードゲームの対戦など多彩な競技でにぎわった
中部地域SIer連携会は、会員各社が得意とする技術を活用し、六つの体験コーナーをそろえた。豊電子工業(愛知県刈谷市)は、ロボを直接手で動かし教示するダイレクトティーチングを用いた「習字ロボット」を紹介する。来場者が書いた文字や絵をロボアームが再現。専門的な知識なしでもティーチングできることが実感できる。近藤製作所(愛知県蒲郡市、近藤茂充社長)は、ロボの動きの精度を体感できるゲーム「3Dスイスイボード」を出品する。幅1・5センチメートルほどの狭いコースの壁に触れずに、金属棒をスタートからゴールまで動かす速さを、来場者とロボが競う。ロボは直角移動だけでなく、立体的なコースもスムーズに動くことが可能。競争を通じて、ロボの動作精度を体感できる。
また、田口鉄工所(岐阜県大垣市)と近藤製作所は共同で、射的でロボと対決するコーナーを設ける。ロボの動作の正確性や再現性の高さを体感できる。
バイナス(愛知県稲沢市)のコーナーでは、教育用ロボ実習装置「ロボトレーナー」の操作体験が可能。ダイレクトティーチングによる直感的な操作を学べる。エヌテック(岐阜県養老町)は、複合現実(MR)の体験コーナーを設ける。専用ゴーグルを装着することで、データ上のロボや機械を現実空間で見ることができる。スターテクノ(愛知県岩倉市)は双腕ロボを操作して景品を落とす、クレーンゲームを紹介する。タブレット端末からの直感的な操作が可能。ロボ導入のハードルを下げる。
次世代ロボットエンジニア支援機構は、フライングディスク射出ロボを使った「フリスビー的当て競争」を実施する。高低差のある的にフライングディスクをいくつ当てられるかを、来場者とロボが競いあう。動作の正確性や、操縦性の高さを体感できる。全て無料で、予約は不要。
次世代を担う子どもや学生らがロボについて学べるだけでなく、ロボや自動化設備の導入を考える来場者にとっても性能や機能を体感できる機会となりそうだ。
現場で役立つ講演に注目 併催イベントやワークショップ
-
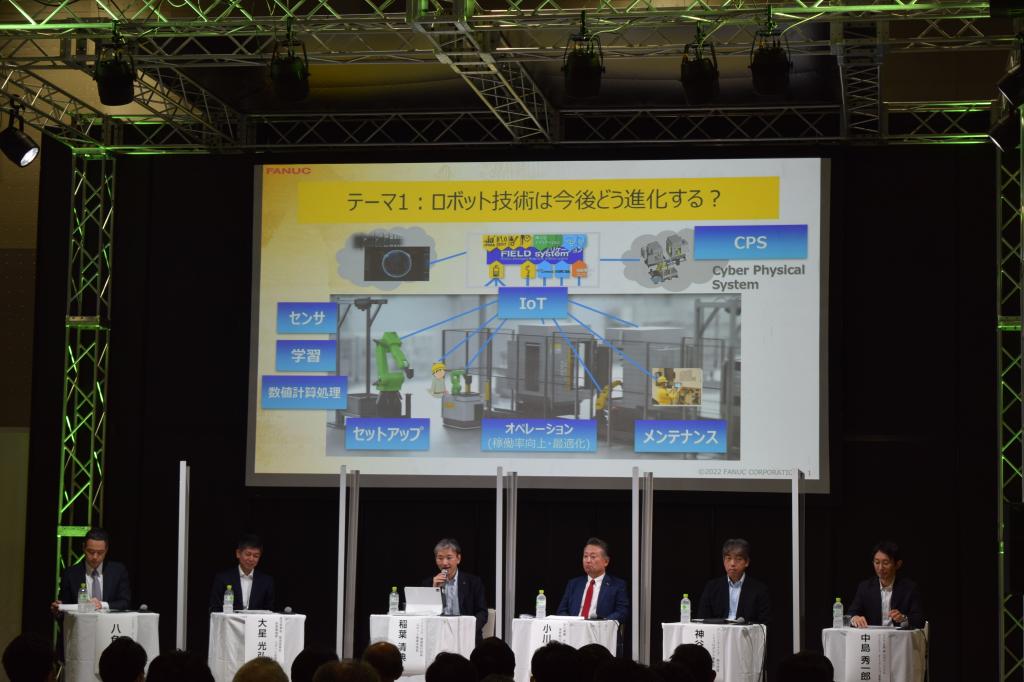
豪華な講師陣に、満員となるセミナーも多い
このほか、主催者による多彩なセミナーにも注目が集まる。展示ホールCのメーンステージにて、毎日テーマに沿った催しが開かれる。開催初日の4日は「ロボットが現場を変える」をテーマに二つの基調講演を実施する。「最新のロボットシステムが実現する『現場』とは」を主題に、安川電機、上席執行役員中国統括ロボット事業部長の岡久学氏による「安川電機が考える未来工場~進化する姿~」、Mujin(東京都江東区)CEO兼共同創業者の滝野一征氏が「ソフトウェア次第で自動化設備能力が数倍変わる時代到来 知能統合プラットフォームが実現した次世代DX工場・倉庫」のタイトルで基調講演を実施する。
5日は二つの併催イベントを開催。午前には愛知県が25年12月に同展示場で開催される国際ロボット競技会「ワールド・ロボット・サミット(WRS)2025」を記念したシンポジウムを開く。テーマは「ロボットとAIによるモノづくりの未来」で、デンソーウェーブ(愛知県阿久比町)のFAプロダクト事業部製品企画室室長榎本聡文氏、オムロンサイニックエックス(東京都文京区)のロボティクスグループPrincipal Investigator濱屋政志氏による基調講演のほか、「未来のモノづくりを考える」をテーマにしたパネルディスカッションを実施する。パネリストにはオムロンサイニックエックスのロボティクスグループPrincipal Investigator、濵屋政志氏、SIer協会会長の久保田和雄氏(三明機工社長)、WRS2025モノづくりロボットチャレンジ競技委員長の琴坂信哉氏(埼玉大学准教授)が登壇。WRSが果たす社会的役割や、ロボの製造現場での活用術などを語る。午後からはSIer協会による「SIer‘s Day in 中部」が開かれる。
最終日の6日は「ロボットでこんなことも!最新活用法」をテーマにボーイングジャパンの先端技術・ロボティクスエンジニア、ハテム・アブデルハミード氏が「狭小スペースにおける作業自動化への挑戦」、次世代ロボットエンジニア支援機構の代表理事川節拓実 氏が「地域のエンジニアが地域の子どもたちを育成する 次世代エンジニア育成プログラム」と題した特別セミナーを開く。聴講は全て無料で、公式サイトからの申し込みが必要。各講演の定員は300人で先着順。
さらに展示ホールEでは出展各社が自慢の製品や技術を紹介する「出展者ワークショップ」も開催される。会期中は毎日5社程度が登壇し、自社の取り組みや自動化の事例、最新のシステムについて解説する。全て聴講は無料で、一部のワークショップは公式サイトから聴講予約が可能だ。
各社の出展製品や技術について、開発者や担当者などから直接解説を受けられる機会となる。

