-
業種・地域から探す
続きの記事
大分県座談会2025
「新生・シリコンアイランド九州」の発展に向けて、いよいよ半導体生産を通じたサプライチェーン(供給網)の活性化が動き出す。熊本県菊陽町に進出した半導体受託製造(ファウンドリー)の世界最大手、台湾積体電路製造(TSMC)の第1工場が2024年末に量産を開始した。第2工場は27年末の稼働を目指しており、その経済波及効果は域内外の投資活動意欲を高めている。大分県も半導体関連産業が集積、振興策に力を入れている。そこで今回、佐藤知事をはじめ九州の半導体関連産業をけん引する代表や識者などによる座談会を開き、意見交換してもらった。
大分県の産業集積と強み
【 出 席 者 】
大分県知事 佐藤 樹一郎 氏
九州半導体・デジタルイノベーション協議会会長
(ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング社長) 山口 宜洋 氏
九州経済調査協会
常務理事兼事業開発部長 岡野 秀之 氏
立命館アジア太平洋大学
学長 米山 裕 氏
大分県LSIクラスター形成推進会議
企画委員長(スズキ社長) 鈴木 清己 氏
(司会)日刊工業新聞社西部支社長 武田 則秋
半導体関連産業 発展の好機
-

大分県知事 佐藤 樹一郎 氏
―まずは佐藤知事からモノづくり立県として大分県の現状を教えてください。
佐藤 本県の中核産業は半導体や精密機械、さらに自動車などです。素材産業が集積する臨海コンビナートがある大分市は、国による「2023年経済構造実態調査 製造業事業所調査」に基づく「市区町村別統計」から近年、北九州市を抜いて九州で一番の製造品出荷額を誇ります。
中でも半導体産業はテレビやスマートフォンといった日常品に限らず、次世代自動車など先端産業も支える重要な産業基盤です。大分市と中津市周辺には半導体製造装置や洗浄、研磨、テスト装置など関連企業が集積し、大分市内には大手半導体デバイスメーカーのソニーセミコンダクタマニュファクチャリングやファウンドリーのジャパンセミコンダクターの基幹工場がそれぞれ立地します。
05年には全国に先駆けて産学官連携組織「大分県LSIクラスター形成推進会議」を創設。当初は44会員からスタートした組織も、現在は約3倍の133会員が参加して半導体関連産業を後押ししています。
最近は人工知能(AI)が注目されるように、半導体産業に新たなイノベーションが起きています。一方で半導体の安定供給が最重要課題となり、経済安全保障上の重要性が再認識されたことから、国際的にサプライチェーンの再構築も進んでいます。
こうした中で熊本県菊陽町にTSMCが進出しました。大分県庁からTSMCまで車を使うと2時間程度です。大分県から熊本県を結ぶ中九州横断道路が完成すると、両県の距離感はさらに近くなります。TSMCの進出は本県の半導体産業を大きく発展させる好機ととらえています。
技術や情報 国内外へ発信を
―半導体産業の振興に向けた大分県の強みを教えてください。
山口 九州半導体・デジタルイノベーション協議会(SIIQ、シーク)の会長の立場からお話させていただきます。当協議会は半導体、エレクトロニクス関連産業の振興に取り組んでいます。TSMCの進出をきっかけに九州全体で多くの半導体関連投資が生まれ、新生・シリコンアイランド九州の機運が高まっています。そこで半導体のサプライチェーンを、入り口から出口までバリューチェーンととらえると、ポジティブな経済循環ができると思います。
今後、半導体関連産業との新たなつながりをつくるには、インフラ整備も必要ですが、九州から国内外に向けて技術や情報を発信することが大切です。それにより半導体産業を一段と九州に根付かせ、人材も集まるようになると思います。
大分県には推進会議のように半導体産業を後押しする強い基盤もあります。九州の半導体産業を、さらにけん引する組織的な活動の広がりを期待しています。
地場企業にもチャンス到来
岡野 20年代に入り半導体産業は大きく変化し、地場企業にもチャンスが到来しています。半導体産業を取り巻く変化を三つの視点で整理しました。
まずは「市場」。半導体産業をけん引するテクノロジードライバーは、AIやクラウドなどデータセンターのような社会基盤となるデジタルサービスで、成長する先端ロジック半導体市場です。二つ目は「技術」。ムーアの法則に代表されるようにデザインルールの微細化が限界を迎えるなかで、複数の異種チップをつなぎ合わせる先端パッケージの3D化技術が重要になっています。三つ目は「地政学」。経済安全保障の問題から米国、台湾と日本が手を組みながら新しいバリューチェーンをつくる流れがあります。
-
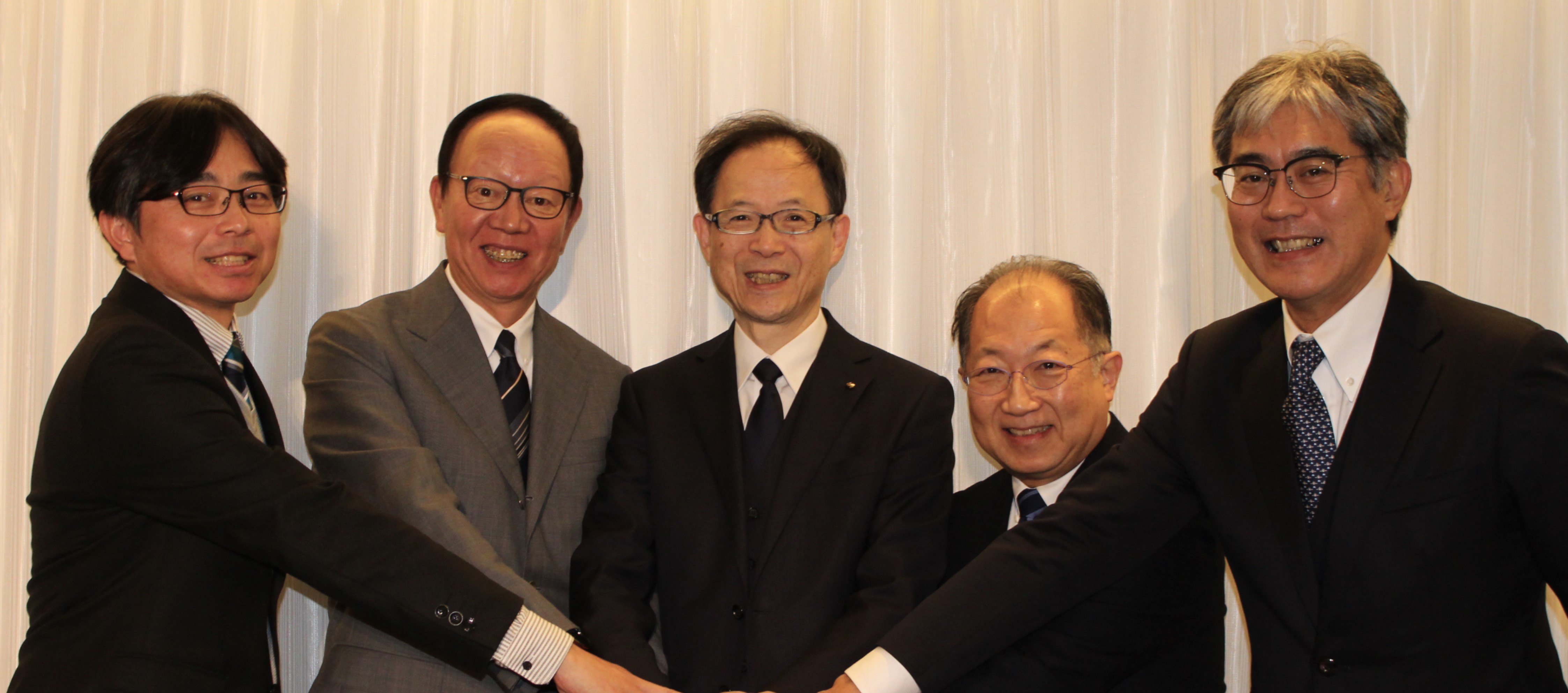
半導体関連産業の振興を誓った
大分県内にはジャパンセミコンダクターや半導体後工程請負業(OSAT)の米国アムコー・テクノロジーが立地します。さらにパッケージ、テスト事業など後工程を得意とする地場企業が集積しています。こうしたことから、先端パッケージ市場への地場企業の挑戦や、前工程と後工程が集積する技術の強みを結集し、デバイスを早く試作して事業化できる環境がつくれれば面白いと思います。
全国の関連組織と連携強化を
鈴木 大分県LSIクラスター形成推進会議では企画委員長を務めています。「産学官」の連携が大分県の特徴であり、強みです。活動は会員の強みを生かし大分県が「品質・コスト・納期」で国際的な競争力を有する生産拠点となるべく、①研究開発②人材育成③販路開拓④企業間交流などを進めています。
現在TSMCが注目されていますが、台湾との交流は以前から行っていました。11年に台湾電子設備協会と覚書(MOU)を結んで、日台双方で商談会を毎年2回開催しています。国内で行うときは熊本県とも連携して相互に開催しています。
また2年半前に九州経済産業局とシークで設立した九州全体の産学官連携組織「九州半導体人材育成等コンソーシアム」は、推進会議のメンバーが多く参加し、サプライチェーン強靱化ワーキンググループの座長を務めています。
全国各地で半導体のコンソーシアムが立ち上がっていますが、大分県のように総合的、かつ活発に産学官で後押ししている例はありません。今後も各県、各地域のクラスターともっと連携強化して、引き続き半導体関連産業をけん引できるようクラスターの強化を目指します。
一方で私もバリューチェーンの構築が重要だと思います。全国有数の温泉観光地がある大分県は地熱やバイオマス発電といった再生可能エネルギーが豊富です。今、GAFA(米巨大IT企業)を含めて世界的にはカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)への要請が高まっています。
脱炭素エネルギーが安定的に入手できる事業環境は、企業の電力調達ニーズを大いに満たすことができます。この強みを武器に、さまざまな企業を世界から呼び込むことができると思います。
国際ビジネス人材育成に貢献
米山 立命館アジア太平洋大学(APU)は別府市にキャンパスを構え、現在世界111カ国・地域からの国際学生3084人と、国内学生3196人の計6280人が在籍します。国内学生の多くも国際的な活躍を志向し、多文化環境のキャンパスにおける活動に加え、さまざまな課外活動のプログラムに参加します。キャンパス内の公用語は英語・日本語。その卒業生は母国語と外国語能力を生かして国内外の企業や公的機関で活躍し、日本企業の国際的な発展にも貢献する教育を行っています。
近年APUの学生に対する企業からの需要はマネジメント人材です。特にTSMCの進出により、台湾から来られた方をつなぐ国際人材としての学生ニーズが高いです。今後APUが大分県の半導体産業の発展に大きなリソースとして貢献できると考えています。

