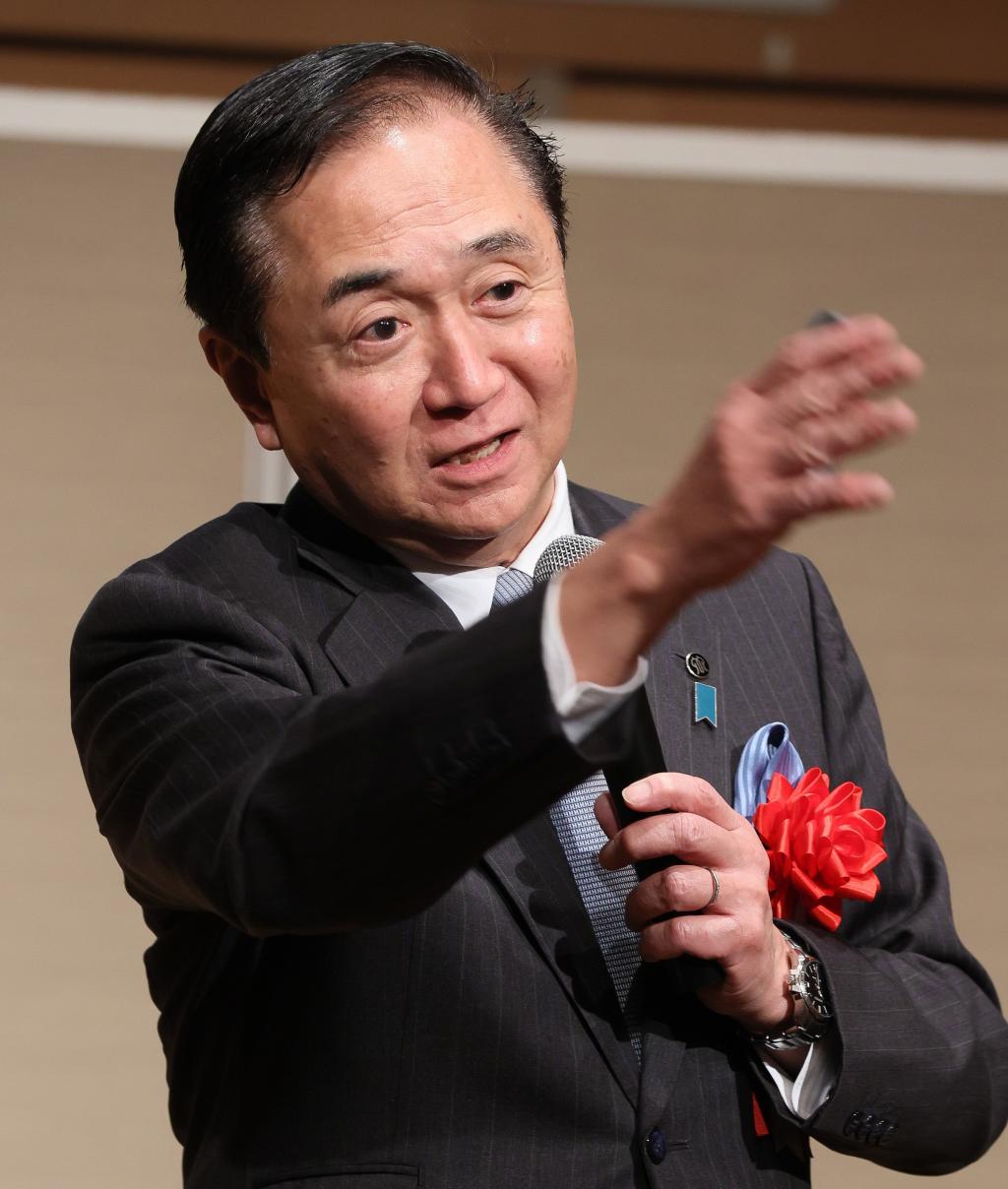-
業種・地域から探す
神奈川産業人クラブ 40周年
神奈川産業人クラブ(中村幹夫会長=大和ケミカル会長、厚木商工会議所会頭)は1月26日、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ(横浜市西区)で2024年の新春特別講演会を開いた。産業能率大学の鬼木和子学長が、ナラティブの重要性をテーマに「今だからこそ問われる上司(企業経営者)の対話力」と題し講演。「論理・科学」だけでなく、個別性の高い出来事を語る・語られる「ナラティブ」の重要性が増していると訴えた。神奈川県の黒岩祐治知事は「県民目線の神奈川県政」と題し、相手の目線で考える大切さについて話した。
産業能率大学 学長 鬼木 和子氏「今だからこそ問われる上司の対話力 ―新春特別講演会
「知識は実際に役立ってこそ価値がある」との建学の精神のもと歴史を紡いできた産業能率大学は、創立以来、時代を先取りした取り組みを進め、産学・地域連携にも力を入れてきました。そのような教育環境で重要なのは全く異なる背景、異なる日常を持つ人と人とがいかにうまく協働できるかということです。お互いに分からないことばかりだが、まずは話をしよう、話を聞こうという姿勢を持つことが重要です。双方向のやりとりこそ対話であり、人と人とのコミュニケーションの方法がより複雑化、多様化する現在、重要性が増しています。
時代の転換点を迎えている現社会を教育現場の視点で概観すると大学設置基準の改正も相まってコロナ禍で加速したオンライン授業の活用が大学教育のDX化に拍車をかけています。海外派遣学生、外国人留学生の受け入れ、社会人の学び直しが本格化すれば同質性の高い現在の学生構成が大きく変わります。同様に高校と大学、地域、産官学の各連携や文理融合などにより、「分ける」から互いに持ち味を発揮して連携する「和える」世界が急速に広がることが予測されるでしょう。
就職活動も多様化しています。価値観の異なる学生がそれぞれのスタイルで挑戦。大学には一元的な指導が通らない時代になり、各学生に合わせたキャリア支援が求められています。企業も「選ぶ」採用から「育てる」採用へとシフトする傾向が徐々に高まるのではないかと思います。
そのような変容の途上にある現社会にあって、私たちは何をよりどころにできるかという問いに応えるため、「教育の過程」を著した米国の教育心理学者ブルーナー氏が晩年取り組んだナラティブ研究の著書の一説を紹介します。「我々は二つの世界を受け入れている。一つは簡潔によく定義されたパラダイムの世界であり、もう一つは不十分だが魅力的なナラティヴの世界である。たしかに我々の世界が狭くなるのは両者の結びつきを見失う時である」。この一説は本日のテーマ、現社会におけるナラティブの意義とその対極にある論理・科学的思考との関係性が明示されていると考えます。
意味ある対話の場作る「ナラティブ」重要性増す
私たちは近代以降、科学・技術の進歩のもと産業資本主義の発展を是とする歴史を紡いできましたが、すでにそうした一元的価値観で世界を捉えることはできません。しかし、その進歩と発展を支える論理・科学的思考の重要性は厳然とあり、他方、私たち一人一人の声をかき消さないことの大切さに目を向けると、人と人との関係性から生まれる対話の重要性はさらに重みを増しています。人の営みは対話的行為で成り立っています。ある事柄に関する解釈は人の数だけあり、人と人は「分かりあえなさ」から出発するものですが、時間を費やして対話を続けることで問題が解消し、そこから新たな価値が生まれ、イノベーションにつながります。大切なのは双方に意味ある対話を重ねること。その意味で真の対話力とは対話を重ねる行為そのものということです。組織において責任ある立場にある方であればあるほど、対話の場を作る先導役になることが重要な役割と考えます。
その対話で成り立つのがナラティブ。ナラティブは「語り」「物語」と訳されますが、一つには語り手と聞き手による対話によって成立する関係性の言語という意味があります。もう一つは物語の側面で「昔々ある時に…」とあるように、具体的で個別性が高く、時間軸に沿った形式で、人が生きる現実を著すのに不可欠な形式です。人はロジックだけではなく常に物語的に生きているということになります。それは言語脳科学の観点からも明らかなようです。
近代科学が進む中で脇に置かれてしまったナラティブですが、近年、その有用性が多様な分野で見直されています。例えば医療。科学的な裏付けに基づく治療だけでなく、患者と医師が対等に対話を重ねる過程で、最も効果的な治療方法を探るというナラティブ的な手法が注目されています。時間というコストはかかりますが、丁寧に対話を重ねることで疾病の真の原因が分かり、患者には納得いく治療を受けることにもながります。研究分野でも著者である「私」の言葉で他者の語りを丁寧に取り上げ、普遍性、汎用性を求めない結論に導くスタイルが認められる論文も多数世に出ています。
このようにナラティブの可能性を期待する半面、SNSなどの急速な普及により、個別の「小さな声」がさまざまな媒体を通して拡散し、それが真実であるかフェイクであるかの検証もないまま、私たちを扇動する「大きな声」にすり替えられ、個人が攻撃されたり情報操作に使われたりしまうことが日常的に起きています。時にはその「大きな声」が支配的になってしまうという脆弱な世界に私たちは生きています。
そのようなリスクを抱える現社会を生きる一つの方法として、フェアで闊達な意見が交わせる複数のコミュニティーに身を置くことが挙げられます。各メンバーが信頼関係で結ばれていれば、多様な価値やナラティブを吸収できる環境づくりが進むでしょう。どんな組織も言語で成り立っています。対話によって、より豊かに次世代を歩む素地が形成されれば、社会全体を動かす原動力になります。その意味でも、組織において責任ある立場にある方には常に、誰に何をどう伝え、誰と語り合い、いつ誰からじっくりと話を聞くかなどの場の構築を先導し、協働による目標設定や展望、使命の共有化を担うことが重要ではないかと考えます。
県民目線の神奈川県政/神奈川県知事 黒岩 祐治氏
デジタル行政で優しい社会へ
私は日頃から「目線」という言葉を大切にして、県職員にはさまざまな場面で「県民目線」を意識するよう話をしています。
コロナ対策がその一つです。国、県、市町村で支援策が分かれており、利用する県民、事業者はそれぞれ自ら確認する必要がありました。そこでこうした支援策を「県民目線」「事業者目線」でそれぞれ整理したチラシを作成。一目瞭然で理解しやすくなりました。
90回を超えた「県民との対話の広場」も県民目線で展開してきました。キャスター経験を活かして私自身が司会進行を担い、県民の話をうかがい、話を紡ぐことで具体的な政策につなげてきました。
選挙期間中に医療的ケアが必要なお子さんとその家族とオンラインで対話をした際、「自分の子どもに一度でいいから映画館で映画を見せるのが夢だ」という声に接して驚きました。医療機器をつけていたり、ベッドのまま移動する必要があるため普通の映画館には行けないということでした。そこでボランティアや協賛企業の力も借りながら「医療的ケア児らの目線」に立った特別映画鑑賞会を実現しました。
コロナ禍では「LINE新型コロナ対策パーソナルサポート」を開発し、ひとり一人の不安解消を図りましたが、これはデジタルを活用した「患者目線」に立った支援でした。
ライドシェアの検討も「利用者目線」を徹底。ある地域のある時間帯ではタクシーがつかまらない。それなら地域と時間帯を限定して一般ドライバーの有償運転を認め、それをタクシー事業者と一体となって進めようという「神奈川版ライドシェア」を提案。4月以降、三浦市で実証実験が始まり、全国展開にもつながりそうです。
人は自分の目線で考えがちです。しかし、相手の目線に置き換えて考えれば接し方も変わってきます。会社の中では部下の目線に立ち、家族の中では配偶者や子どもの目線に立って考えてみることです。目線を変えることは優しさにつながります。神奈川県はこれからも「県民目線のデジタル行政でやさしい社会」の実現を目指し、さまざまな施策に取り組んでまいります。
追悼 神奈川産業人クラブ 元会長 岡本 満夫氏
神奈川産業人クラブ会長を2017年6月から20年5月まで務めていただいた、元アマダ会長・社長で名誉相談役の岡本満夫氏が2月、逝去されました。ご尽力に感謝を申し上げ、謹んでご冥福をお祈りします。