-
業種・地域から探す
歯車工業会の取り組み
「ギヤカレッジ」対面復活
-
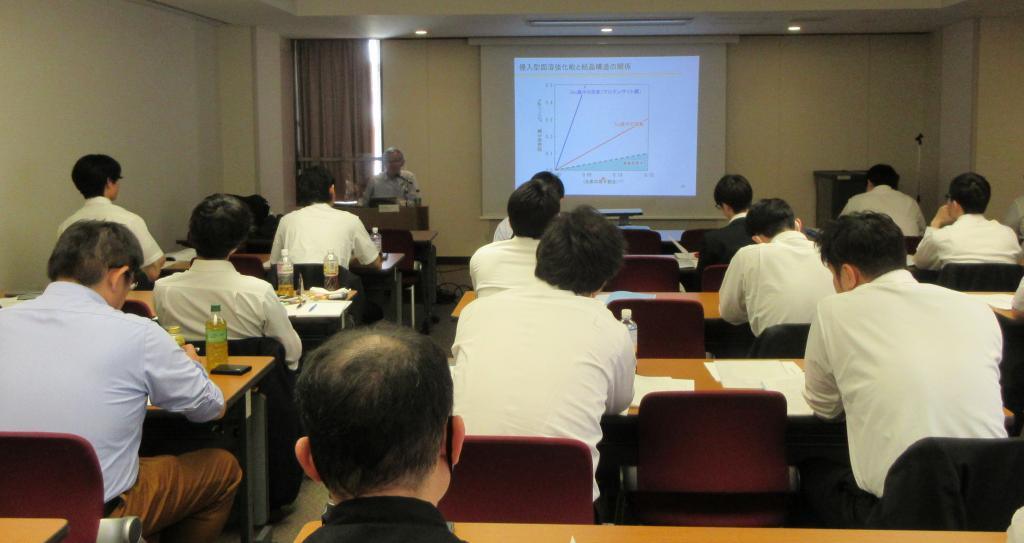
2019年度以来の対面が復活した歯車技術講座「JGMAギヤカレッジ」
日本歯車工業会(JGMA)の活動の大きな柱は「規格事業」「国際交流事業」「教育事業」の三つ。教育事業の中でも特に力を入れているのが歯車技術講座「JGMAギヤカレッジ」だ。企業の中核を担う人材の育成を目的としている。一方、2022年には高齢者の知識や経験を次の世代に伝承し、また、高齢者自身が活躍することで企業の力を高めようと、高齢者雇用推進に向けたガイドラインをとりまとめた。
JGMAは歯車の設計・製造技術を修得し、社内の中核リーダーを目指す技術者の育成を目的として、11年から歯車技術講座「JGMAギヤカレッジ」を実施してきた。これまでに基礎講座「マスターコース」512人、応用講座「プロフェッショナルコース」249人が修了している。
今年度は5月26日にスタート。受講はマスターコース30人、プロフェッショナルコース8人。マスターコースの場合、70時間以上の講義と、最大9日間の実習という、かなりハードな内容だ。
コロナ禍の影響で、20年度は中止、21、22年度はオンライン実施となったが、今年度は対面での実施が再開された。フェース・ツー・フェースで受講し、また、チームを組んで実習することは「同期の連帯感」を醸成し、ネットワークづくりに大きな効果がある。JGMAギヤカレッジ企画・運営委員会の田中文彦委員長(オージック会長)は「受講生が大いなる可能性を秘めたコミュニティーを築き、互いに学び合い、刺激し合い、ともに成長していくことを期待している」と、対面復活に手応えを感じている。
高齢者ガイドライン策定
JGMAは22年11月、「歯車製造業 高齢者の活躍に向けたガイドライン」を策定した。高齢者の高い満足度を業績につなげる仕組みづくり、貢献度に応じた処遇、高齢者の特性に応じた職務開発と配置など、六つの指針を示している。
経験や技術を蓄積してきた高齢者について、単に少子高齢化に伴う労働力不足への対応にとどめず、現在と将来の歯車製造業をもっと強くするため、積極的に活用することが重要との考えだ。
産業の競争力強化には歯車製造業の将来を担う若手・中堅の技術者・技能者の成長が必須だ。高齢者には教え手として自身の持つ技術や技能、知識や経験を伝授する役割が期待されている。そのためには、高齢者が自分の持つ強みを発揮しようとする意欲を衰えさせない仕組みづくりが不可欠になる。

